|
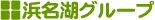
 指導者研修会にて、講話をする小松さん
指導者研修会にて、講話をする小松さん |
オリンピックをめざすために中学校を去った小松さん。ヤマハ発動機への入社は、ヨット活動のチャンスがより広がると考えたからでした。
「ヤマハでは舟艇設計部に所属しました。試作艇のテストセーリングを中心に、さまざまなヨットの開発に携わることで、設計者や技術者からヨットの構造的な知識を学ぶことができると考えたからです」
確かに、練習だけがセーリングの腕を上げるための手段ではありません。ヨットの構造など技術的な知識を身につけることは、選手にとって大きなアドバンテージになります。小松さんは、仕事を通じて疑問に感じたことを、どんどん設計担当者や建造担当者に質問していきました。
もっとも当時、同社にヨット部はなく、小松さんは一社員として朝から夕方まで時間通りに勤務していました。大会に出るときはヤマハ所属の小松一憲選手という形になりましたが、いわゆるセミプロのような優遇措置は、まったく受けていなかったのです。
「よく誤解されるのですが、あくまでも一社員としての入社でしたから、入社当時、仕事でヨットのことを学べても、平日の昼間に練習するということはありませんでした。ただ、私を含めてヨットの選手活動をしている社員数名が、職場にほど近い浜名湖畔の寮で生活していたのは幸いでした。なにせ寮の目の前が湖ですから、毎日、早朝練習で汗を流してから出社することができたのです。もちろん、土日になると仕事を忘れて1日中練習に励んでいました」
 OPヨット指導者講習会にて指導する小松さん
OPヨット指導者講習会にて指導する小松さん |
ヨット開発の仕事が軌道に乗ると、何人かの有名選手に声をかけて試作艇をテストセーリングしてもらうようになっていきました。居ながらにして、トップレベルの選手たちと交流できるわけですから、小松さんにとっては願ってもないことでした。
「よく、土日にかけて一緒に合宿してもらいながら試作艇に乗ってもらいましたが、そんな活動が定着すると、やがて浜名湖に集まる選手たちのことを、ヨット界では『浜名湖グループ』と呼ぶようになっていました」
毎週のように浜名湖に集まるヨット選手たち。やがて、その浜名湖グループが母体となって、日本では初となるヨットのオリンピック強化活動が始まったそうです。
「1980年のロサンゼルスオリンピックに向けて、当時、日本ヨット協会のオリンピック担当委員長を務めていた松本富士也さん
(B&G江の島海洋クラブ代表)
が、『浜名湖グループの活動を、協会がバックアップする』と言ってくれたのです」
仕事をしながらではあったものの、小松さんはヨット漬けの日々を送ることになっていきました。日誌を振り返ると、年間220日もヨットに乗っていたときがあったそうです。
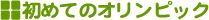
転職は悩んだ末の決断でしたが、ヤマハに入った小松さんは飛ぶ鳥の勢いで国内大会を席巻していきました。入社して2年後の1974年に、470級全日本選手権を奪取。以後、76年に1回だけその座を他に譲りましたが、79年まで日本一の座を守り続けることになったのです。その1976年は、特別な年でした。小松さんが、初めて470級ヨットでオリンピックに出場した年だったからです(モントリオール・オリンピック)。成績は10位。これは、2004年のアテネ・オリンピックで関/轟ペアが銅メダルを獲得するまで、日本の470級男子選手としては最上位の記録でした。
「モントリオールでの微風レースは、忘れもしません。中盤まで2位につけていたのに、急に風がシフトして一気に20位台まで落ちてしまったからです。これさえなければ、総合成績でもっと上に行けたはずでした。それ以降、悔しくて悔しくて、もう1回、もう1回と言っているうちに、気がつけば4回もオリンピックに出ることになったというわけです」
初めてのオリンピックでは苦い経験もありましたが、オリンピックに出場したことで小松さんの人生観が大きく変わっていきました。
「モントリオールで、何もかもが変わったという感じでした。それまで私は、すべて1人で決断し、1人でヨットの腕を磨き、1人で苦労してきたと思っていたのですが、オリンピックに出ることで、実は私の人生もいろいろな人に助けられていることを知ったのです。オリンピックに出ることが決まると、本籍を置いていた遠い秋田の親戚から励ましの声が届けられ、地元の新聞記者もわざわざ取材に訪れてくれました。また、モントリオールに入ってからは日系の方々から激励され、とても勇気が湧きました。このような人の輪のありがたさを、オリンピックの舞台に立つことで知り得たのです」
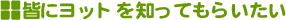
モントリオールから日本に戻ると、仕事の面でも大きな変化が生まれました。
「入社当時は、試合に出るにも休みの申請を出し、自費で参加していました。全日本選手権で勝って、初めて試合のエントリー費用が認められた次第です。それがオリンピックをきっかけに、ヨットで使う交通費は経費となり、試合で仕事を休んでも公休扱いとなりました。幸いにも、私が所属していた当時の設計部で部長をされていた堀内浩太郎さんは、かつて漕艇でオリンピックに出られた経験をお持ちでしたので、上司としてとても理解があったのです」
待遇面ばかりか、仕事の内容も変わっていきました。周囲がオリンピック選手を放ってはおかなかったのです。
「モントリオールでは最後のレースが悔しくて、もっと練習に励まないと世界の壁は破れないと痛感しましたが、その一方、日本に帰ってからは、皆に愛されながらヨット活動をする喜びを知ることができました。ヤマハのヨット普及活動の一環として、全国をまわりながらセーリング講習会を開いたのですが、どこに行っても『小松選手だ!』、『小松選手が来たぞ!』といって、たいへん温かく迎えられたのです。握手を求められ、励ましの言葉をいただくたびに、このような心温かい人たちにも、ぜひヨットを楽しんでもらいたい、そのために自分ができることがあれば、なんでも協力したいと思うようになっていきました。そして、自分はもとより、大勢の人をヨットに導いてしまうオリンピックの効果のすごさに驚きました」
ヨットの開発もさることながら、普及の仕事にも力を入れるようになっていった小松さん。その甲斐あって、1970年代後半から80年代にかけて空前のディンギーヨットブームが到来。ヤマハをはじめ、さまざまなメーカーが数多くのディンギーヨットを生産し、各地でローカルレースが盛んに開催されるようになっていきました。※続く
|




