|

水野:前々回で述べたように、選手の自主性に任せて全日本7連覇を達成したときの神戸製鋼ラグビー部はアマチュアスポーツにおける理想の姿とされていますが、誰もがやみくもに自主的な練習を重ねても強い選手にはなれません。「自分で自分のプレーを評価できる」、言い換えれば「自分と対話ができる人間」になれなければ、神戸製鋼ラグビー部のような理想像は描けないのです。
そのような選手になってもらうために、私が何を教え子たちにしているかと言えば、それはどんなスポーツにも言えることですが、基本練習の繰り返しです。「してはいけない」、「やらねばならない」という基本形を徹底的に強制しているのです。多くの人が、勝つパターンを身につけたいと実戦練習を求めがちですが、いくら仲間内で実戦練習をしても実際の相手が強ければ簡単に負けてしまいます。実戦とは相対的なものですから、そのような練習での上達にはあまり意味がないわけです。一方、基本の繰り返しとは、言うなれば自分との対話です。基本練習で毎日のように自分と対決して得た上達は、絶対的な上達となって身につくのです。
基本とは、先人たちによる長い経験の中で培われたノウハウの凝縮です。あるレベルに達した選手が初めて「これは大事だ」と気づいたことの積み重ねなのです。ですから、そのようなことは初心者には分かりませんし、「理解しろ」と口で言って簡単に納得させられるものでもありません。それなら、彼らにどうやって伝えたらいいでしょうか? 答えは1つしかありません。指導者は、いまやっている練習がどんな役に立つかなどは選手に分かってもらわなくても構わないという気持ちになって、とにかく強制するのです。基本の徹底、これはスポーツにかぎらず、あらゆる教育の第一歩だと思います。
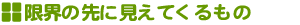
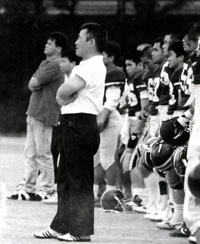 |
水野:自主性イコール善で、強制イコール悪という見方をされやすい昨今ですが、これだと決めたことは、人間、どんなことでもとことん打ち込むべきです。そのための強制は、あってしかるべきだと考えます。技の習得に関して、「これをやれ!」と強制させられたことを懸命になって打ち込んでいくと、「もう無理かもしれない!」という限界が見えてきますが、それでもなお努力すると本当の壁にぶち当たります。そのとき、「これでもう無理だ。でもちょっと待てよ、だったらこういうやり方もあるんじゃないのかな」という閃きが自分の中から見えてくる瞬間が出てきます。そうすると目の前がパッと開けて、いままで難しいと考えていたことが、「なんだ、こんなことだったのか」と簡単に認識できるようになっていきます。
あらゆる場面でそのような壁を乗り越えた選手になると、こちらが「君には、今度の試合でこういうことをしてもらいたい」と言うだけで、彼は自分で解決策を考えてきます。つまり、自主的な判断ができる選手になったというわけです。
弱いとされるチームでも、「我々は勝つのだ!」という意識を徹底させて、とことん練習に励んで試合に挑んでいくと、「これ以上はできない」という限界が見えてきますが、そこで初めて「だったら、どうしたら勝てるのか?」という問答が自分自身の中で沸き起こります。己の限界、己の力をはっきり知ることができ、そのうえで自分なりの対処法を冷静に考えることができるのです。こうした経験は、人生の財産になると常々学生たちに言っております。
 |
さて、己の限界、己の力を知ることができて、どうしたら勝てるのかという壁に当たると、「やれないことはしない」、「やれることは徹底する」という方策が浮かんでくるものです。この答えは、いくら頭で考えても出てくるようなものではありません。そのために練習があるわけで、練習とはすなわち限界への挑戦であるわけです。つまり、限界を知るという認識の行為は行動の上にあるわけで、考えて認識できるものではないのです。考えて得るものは理解であって、それは認識の助けにしか過ぎないのです。認識とはもっと肉体的なものであり、だからこそ「体で覚える」ことが大切なのです。人間の体は、頭より何十倍も賢いものなのです。
最近の我が国は、おしなべて自主性を尊重する風潮にありますが、選手をおだててヤル気を起こすなどという発想は大きな間違いであり、少なくとも大学生なら、スポーツを通じて「我、なんぞや」という自我を意識できるところまで人間的な成長を遂げてもらいたいと考えています。人につくってもらったヤル気などは、敵に一発やられただけで、あっという間に吹き飛んでしまいます。しかし、強制されたものであっても限界を見て己を知った人間は、あくまでも強いのです。
|




