|
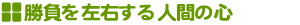
水野:どんなスポーツでも、試合で実力を出すのはとても難しいことです。また、スポーツに限らず、いざという場面でなかなか実力を出せないのが人間というものだと思います。
では、どうして練習を重ねてきたのに大事な試合で力を出し切れない現象が起きるのでしょうか。それは、勝負事というものは戦う前にすでに決着がついている場合が多いからです。つまり、弱い方は戦いを前にして負けを意識してしまうのです。
強い方は、「あんな相手なんて、どうってことはない」と思っていますから、なんの疑いもなく戦いそのものに集中することができますが、弱い方には「相手は強いなあ!
負けてしまうかもしれないなあ」、「大事な場面でミスしたらどうしよう」などと心のなかに余計な思いが生じてしまいがちです。そうなると、もう勝てる精神状態ではないわけです。
なぜ、弱い方はこのような不安を抱いてしまうのでしょうか。それは強い相手のせいではありません。不安に思うのは自分なのです。自分で自分の首を絞めているわけです。
一方、実力は相手より低いものの、徹底的に基本を学んできた選手やチームであれば、「どんな結果になっても、それがオレだ。オレたちなのだ」としっかり自己評価できますから、そうなると「負けることなんて怖くない」、「これで負けても納得できる」という気持ちなって、思い切り全力を出せるようになります。
前回で述べたように、基本の繰り返しとは自分との対話です。ですから、もうだめだというところまで基本練習を徹底していくと、己の限界、己の力をはっきり認識するようになりますから、相手がどんなに強くても自分なりにプレーに集中できるようになるのです。
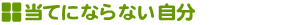
 |
水野:先日、私ども京大は神戸大学に1点差で逆転負けをしてしまいました。そのときの様子を見ていると、主力の4年生選手たちには「もう卒業が控えているから、ここで負けたら後がない」という気持ちが強く、ゲームの展開が悪くなればなるほど精神が緊迫して力が出なくなっていました。確かに相手の神戸大学は強いチームでしたが、その現実をしっかり認識したうえで試合に臨んでいれば負けることはなかったと思います。
試合後、私は「なぜ、お前たちは負けてしまったのか、よく考えてみろ!」と教え子たちに言いましたが、とことん練習すると4年生たちは最後のシーズンで勝ちたくなって気持ちが緊迫してしまい、負けることが怖くなってしまう場合があるのです。
教え子たちに「おい、勝ちたいか?」と尋ねることがありますが、彼らは「勝ちたいです」と口を揃えます。そこで、「だったら、勝つ気があるのか?」と言うと、「もちろん、あります」と簡単に返してきます。
「アホか! そんな簡単な答えしか言えないお前たちに、勝つ気なんてまったくないはずだ」と私は声を上げますが、要は言葉ではなく気持ちが問題なのです。確かに、勝つ気になって練習に励んでいるのでしょうが、真剣になって勝ちを求めたら、「本当に自分は勝ちたいのだろうか?本当に勝ちたいために練習をしているのだろか?」といった疑念が自分自身のなかに湧いてくるはずなのです。己に疑念を抱く心境にまでたどりつけなかったら、勝ちたい気持ちは本物ではないのです。要するに、自分ほど当てにならないものはないのです。人の心なんて、明日になったらどうなっているかわからない、実にあやふやなものなのです。ですから、自分で自分を問い質すことができる人間をめざして、己を鍛えていくわけです。

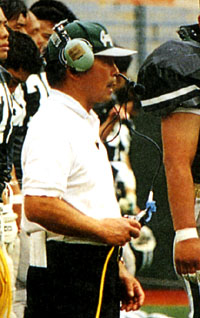 |
水野:基本練習とは自分との対話ですから、何度も繰り返すことで己の心が鍛えられていきます。「やらねばならないこと」、「してはいけないこと」の塊が基本であり、先に述べたように、それは頭ではなく体で覚えることが求められます。こんなことをしたらケガをするとか相手を傷つけてしまうという、いわば先人が築いた体を守るための経験則が詰まっているわけですから、ハードなスポーツであるアメリカンフットボールの場合、このような教えは絶対的な意味を持ってくるのです。
そうした意味からも、私たちは基本を徹底的に練習しているのであり、チームの理念としている「やらねばならないこと」、「してはいけないこと」が守られない場合は、ビンタを張ることも辞さないとしています。
こう述べると、なにやら乱暴に聞こえてしまいがちですが、ビンタを張ることと体罰は、まったく意味が異なります。失敗や力不足を責める体罰というのは全く意味がなく、許されるものではありません。しかし、ある局面においてビンタは指導的な意味や激励的な意味で効果を発揮する場合があるのです。人間、何となく気持ちが乗らない時などパーンとビンタを張られると、ハッと我に帰って「ようし、やるぞ」という気になるものです。
アメリカンフットボールは、「やらねばならないこと」ができなければ大ケガをする場合がありますから、それを怠ってしまったり忘れてしまったりしたときなどには、しっかりと我に帰ってもらわなければ困るのです。また、練習を続けるなかで限界を感じたり弱気になってしまったりする部員についても、その一線を超えてもらいたいためにビンタを張ることがあります。これは激励ですが、こういうことは選手も納得ずくでやらねばなりません。我々の場合は、ヘルメットをかぶっていますから叩くこちらの方が痛いですけどね。
自分が所属するチームは「ここで自分の限界に挑戦するのだ」、「ベストは尽くすものではない、超えるべきものなのだ」、そういう生き方で自己を磨き、知らない自分を知ることに意義を感じる者のみが所属し活動しているのです。学生スポーツを、やるかやらないかは各自の自由意志です。嫌なら辞めるべきです。
最近の若者は学校でビンタなど張られた経験がありませんから、最初に食らうと顔を青くしますが、慣れてくると「がんばったのですが、苦しくなってつい妥協してしまいました。ですから、あのとき張られて助かりました」などと言うようになっていきます。
近年、運動部の体罰が問題化していますが、どんなスポーツでもいい加減なプレーをしたらケガをするものです。そのような事が起きないよう、あらゆるスポーツに「してはいけないこと」、「やらねばならないこと」があるはずで、それを守ってもらいたいためにビンタを張ることは、許されないことではないと思います。
また、ビンタはいけないという理由からか、腹筋運動を何百回やれとか、グラウンドを何十周走れなどという罰を与えるケースがありますが、こうした行為について私は疑問を感じます。貴重な時間を無駄にするだけでなく、大事な部員の体を壊してしまうことにつながるからです。なぜビンタが悪くて、このような無意味な懲罰が良いのか、教育者も保護者もここはしっかり見直す必要があるのではないでしょうか。

『注目の人』の感想をお送っていただいた方に、『KAZI』最新号を抽選で毎月10名様にプレゼントいたします。 郵便番号・住所・氏名・電話番号・感想をご記入の上、下記宛先にお送りください。
郵便番号・住所・氏名・電話番号・感想をご記入の上、下記宛先にお送りください。
●お葉書の方
〒105-8480 東京都港区虎ノ門1-15-16
B&G財団 プレゼント係
●メールの方
 koho@bgf.or.jp
koho@bgf.or.jp
当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせて頂きます。
|
|




