|

 |
体験クルーズのワークショップで
発表テーマについて話し合う様子 |
学校の授業だけでは、なかなか生徒と海をダイレクトに結ぶことができない。もっと実体験に基づいたメッセージを伝えたいと三宅島に渡った海野さん。住まいが決まると、これまでの経験を活かして三宅島の海や山を案内するネイチャーガイドの仕事を始めましたが、第二の人生の始まりには楽しさと苦労が同居していました。
「海が荒れると定期船が休便になって予約がキャンセルされてしまうので、三宅島の民宿業やガイド業はとても難しい仕事です。当初、私もネイチャーガイドだけでは生活できないと思ったので、林を切り開いて畑を耕したほか、素潜り漁をしたり漁師さんから魚を分けてもらったりしながら食材を確保していました。島の自然にどっぷり浸かった生活はとても楽しく充実していましたが、現金収入の面だけは厳しいものがありました」
素潜り漁は誰でもできるものではありません。海野さんは、地元の漁師さんたちに認めてもらって漁業権を手にすることができましたが、これは島の住民として生きる覚悟が相手に伝わらなければ叶うものではありません。
「観光客は初対面でも温かく迎えてくれますが、島に住む人間として三宅島の人たちに認めてもらうには時間がかかります。地域社会の密度が濃くて、地区ごとに住民同士が強い絆で結ばれているからです。これは、どの島でも同じだと思います」
四方を海に囲まれ、常に自然と向き合わなければならない島の暮らし。当然のことながら、そこには同じ土地に生きる人間同士の強い絆が必要です。そのことを理解せずに島で暮らそうと考えても、上手くいくわけがありません。三宅島の自然に憧れて移住したものの、わずか1〜2年で島を去っていく人が少なくないそうです。
「最初から地域社会と関わりを持たずにマイペースを貫くという考え方もありますが、私の場合は地域に根を張った生活を求めていました。ですから、自ら好んで島の行事に参加し、港では漁師さんたちと酒を酌み交わして自分を知ってもらう努力をしました」
海野さんの認知度はしだいに高まり、やがて消防団の一員として活躍。2000年の噴火の際には、地区長として島民の避難を誘導するまでになっていました。
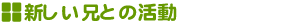
畑を耕し、漁をしながらネイチャーガイドを続けて数年の月日が過ぎたとき、海野さんは思わぬ仕事の誘いを受けました。声を掛けてくれたのは、海野さんが島に来る以前から三宅島の自然に魅せられて住んでいたジャック・T・モイヤー博士でした。
「モイヤー先生が長年手掛けていた、全国の子どもたちを対象にしたサマースクールを手伝ってくれないかと声を掛けられたのです。それまではボランティアに支えられて運営してきたものの、継続的な開催にあたって専門的なスタッフがほしいとのことでした。モイヤー先生が三宅島に住んでいることは知っていましたが、それまで特に深いつながりはありませんでした。振り返れば、三宅島の魅力が私とモイヤー先生を引き寄せてくれたのだと思います。親子ほどの年の差がありましたが、親しみ深いモイヤー先生のおかげで、私にとっては急に年が離れた兄貴ができた気分になりました」
 |
|
体験クルーズの海洋観察で
ソウフ岩について説明をする海野さん
|
モイヤー博士は、三宅島で小学生から高校生までを対象に、島の海を学ぶプログラムを長年にわたって展開していましたが、10年以上も自然環境教育に携わっていた海野さんは願ってもないスタッフ要員だったにちがいありません。海野さんにしても、モイヤー博士が手掛けていたプログラムを手伝うことをきっかけに、水を得た魚のように活躍のフィールドを広げていきました。
「三宅島の小学校は、平成11年度に総合的な学習の時間に関する研究指定校になり、私はモイヤー先生とともにアドバイザーとして授業に関わりました。また、海の体験授業の実践に熱心な小学校の先生の働きがあって、シュノーケリングで島のサンゴを観察する授業も実現しました。こうした校外授業を行うためには学校側の決断が必要です。幸いなことに、校長先生が環境教育に対してとても理解があったので実現することができました」
これらの授業は、平成14年度に総合的な学習の時間が正式にスタートした後も継続され、噴火で避難した後には子どもたちから「噴火の影響を受けたサンゴや野鳥たちは大丈夫だろうか」といった心配の声が続々と上がりました。
「総合的な学習の時間は、全国でさまざまな内容の授業が展開されていますが、三宅島の小学校で行われたこの授業はとても有意義だったと自負しています。もし、子どもたちがサンゴや野鳥の観察を経験していなかったら、噴火で避難した後に島の自然環境を心配することはあまりなかったと思います。しかし、この授業を続けたおかげで島の子どもたちは噴火が島の自然環境にどんな影響を及ぼすのか、自らの力で考えているのです」
サンゴや野鳥は、島で暮らす子どもたちにとっては当たり前の存在で、わざわざ海に潜ったり山に入ったりして観察するような機会はあまりなかったそうですが、この授業を通じて実際にその姿に触れた瞬間、「自分たちの島には、すばらしい宝物がある」と言って感激し、それが島で生きる子どもたちの誇りもになっていったそうです。
海野さんにとっても、やっと本当に自分がやりかたった活動が実現したわけです。その後の展開を考えるうえでも、まさにモイヤー博士との出会いは運命的なものでした。
|




