|
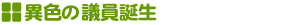
 |
| 海洋クラブ主宰の一日ヨット教室 |
B&G宇部海洋クラブを立ち上げ、ディンギーヨットの活動にも力が入れられるようになった岡村さん。学習塾と野外活動教育という2つの柱を持った塾の経営も順調に推移し、太平洋単独横断後から続けられてきた講演活動と相まって、「教育の岡村」という評判が立ち始めましたが、平成9年、岡村さんは塾の経営権を若い講師にあっさり譲ってしまいました。
「36歳のときに塾の現場から身を引くことを決め、5年がかりで仕事の引き継ぎをして40歳で退きました。というのも、私は勉強を教えながらアウトドア活動の仕事をすることに大きなジレンマを感じていたのです」
元来、岡村さんが目指したのは子どもたちへの野外活動教育。それだけでは生活していけないために学習塾を併設し、昼間は建築の図面を引いていたのでした。ですから、時が経つにつれて、どうしても初志である野外活動教育への思いが強まっていったのでした。周囲からすれば、せっかく評判になった学習塾をなぜ手放すのかと思うところですが、岡村さんの気持ちは変わりませんでした。
平成11年、岡村さんはNPO法人「森と海の学校」を設立。野外活動教育に本腰を入れることになりましたが、そこで思わぬ展開が待っていました。すでに講演や塾の経営で名を立てていただけに、世間が岡村さんを放ってはおかなかったのです。
 |
| ウォークラリー大会のスターターを務める岡村さん |
「塾の現場から退いて、野外活動教育に専念しようと思った矢先、ある友人がやってきて市議会議員の選挙に出ないかと背中を押されてしまいました。それまでは考えたこともなっただけに驚いて1回は断りましたが、声を掛けられたことでいろいろ考えるようになり、私にもその役割が回って来る年齢になったのかなという気持ちになりました。確かに、それまで塾とアウトドアを通じて多くの子どもたちを見てきましたから、教育の面で行政や政治に関わる人たちに対して言いたいことは山ほどあったのです。また、都合の良いことに学校の春休みと夏休みの間は、議会も開いていませんでしたから、私が目指している野外教育活動は従来どおり行うことができたのです」
岡村さんは、ギリギリで出馬を表明したため十分な選挙活動はできませんでしたが、フタを開けてみると、なんとトップで当選。塾やキャンプなどで常に子どもたちと接してきた岡村さんは市議会のなかでも貴重な存在となり、教育や福祉の面で大いに力を発揮することになりました。
現在、岡村さんは「森と海の学校」をはじめとするさまざまな仕事をこなしながら県会議員として活躍していますが、ここで最近行われた県議会で一般質問の前に語ったスピーチを紹介したいと思います(岡村さんの公式ホームページhttp://www.okamura21.com/から抜粋。カッコ以外の文章は原文のまま掲載)。どれだけ岡村さんが人間教育に力を入れているかが伺えると思います。
『四月には県庁にも、新入職員が入って来ます。私は新入社員研修に、講師として招かれることがありますが、必ず「最初の給料だけは、長年育てて下さった、ご両親のために使って下さい」と話をします。
(1つのエピソードですが、初めての給料を手にした)ある新入社員の女性が「ご両親に、夕食をご馳走しよう」とフランス料理の高級レストランを予約しました。
ところが当日、仕事の都合で、少し遅れて、レストランに着くと、お父さんは、顔を見るなり「人を食事に誘っておいて、待たせるとは何事だ」と娘を叱り、その上、食事が始まると「お前なあ、20年間育ててもらった恩を、1回の食事で済ませようと思うなよ」とか、料理を出されるたびに「なぜこんなものを注文したんだ」などと、嫌味を言ったそうです。
そんな時ふと、お父さんの手を見ると、しわだらけの手に、セメントのクズがこびり付いていました。お父さんは、建設会社の現場監督です。
「この手で私を20年間育ててくれたんだなあ」と思ったら、何も言えなくて、今日1日だけは、何を言われても我慢しようと決めました。それでも、お父さんは嫌味を言い続けました。
家に帰って、お風呂に入りながら「お父さんなんか、2度と、食事に誘わない!」と思いました。風呂から上がって、茶の間の前を通りかかると、中から、お母さんとお父さんの会話が聞こえてきました。お母さんが、お父さんに「今日の夕食、おいしかったね」と尋ねると、お父さんが「おれ、人生48年、生きてきたけど、今日くらいうまい晩御飯、食べたことなかったなあ」と答えたそうです。そのとたん、新入社員の女性は、涙が止まらなくて、フトンに入り、思いっきり泣いたそうです。
県庁の新入職員にも「最初の給料くらいは、ぜひ、ご両親のために!」と指導されて如何でしょうか。』

このスピーチでも分かるように、岡村さんは言葉よりも行動に移すことの大切さを常に訴え続けています。前回では、キャンプなどの野外活動を通じて子どもたちにいろいろな場面(役割)を与えることに力点を置いていると述べましたが、それは行動を伴わなければ役割を担うことができないからに他ありません。言葉で教えられるのではなく、自ら行動することで子どもたちは自己責任や仲間をいたわることなどを学んでいくわけです。
 |
| 「平成16年度子ども自然体験キャンプ」での一コマ |
「キャンプや体験航海などで小学1年生がいれば、その子の世話を小学6年生がするようになるし、高校1年生でも班長になれば、夜中に起きて小さい子どものオネショの世話をするようになります。そうした場面をつくってあげるのが私の仕事なのです」
役割が人の立派さをつくり、各々の存在価値を認め合う下地になっていく。それが岡村流人間教育の基本になっていると言えるでしょう。そして、役割を自覚するという行為は座学ではなく体を動かして初めて身につくものである、という持論によって支えられています。
「これまでを振り返れば、私自身も体験すること以外では強くなれませんでした。人間、体を動かさないと気も働かないのです。その意味から、私はより多くの子どもたちを家の外に連れ出したいのです。とは言っても、子どもたちに山伏のような過酷な修行をさせるわけにもいきません」
塾を開いて野外活動教育を始めた当初、岡村さんはかなり厳しい状況を子どもたちに与えて忍耐力を養おうとしましたが、しだいに軌道修正していったそうです。
「単に厳しいだけでは、本当の意味での忍耐や根性といったものは身につかないことを知りました。今でも続けている活動プログラムの1つに、40キロの道のりを踏破するウォーキングがあるのですが、40キロを歩いたから忍耐や根性が身につくのではなく、潜在的な忍耐力や根性があるからこそ、長い道のりを歩くことができるのです」
忍耐することの大切さは、実は普段の生活の中で何かを我慢する体験の中で身についていくものであると、岡村さんは言います。つまり、忍耐や根性といったものは身につけさせるものではなく、さまざまな葛藤を通じて身についていくものなのだと言えるでしょう。そうした体験の場を家庭や学校、社会が子どもたちに与えてあげることが大切になるわけです。
それに気づいた岡村さんは、子どもたちの心に働きかけるような工夫を野外活動教育プログラムの中にも意識的に取り込むようにしていきました。その様子は次回にご紹介いたします。
|




