|

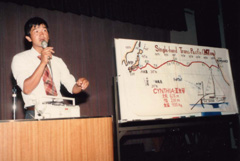 |
| 大好評だったB&G「若人の船」での講演 |
昭和59年、塾開設の準備が進むなか、岡村さんは講演先で偶然にもB&G「若人の船」の参加者を募るポスターを目にすることになりました。
「シンガポール〜バンコクへの船旅で、ちょうど塾を開く前の比較的時間が取れる時期での開催だったので、興味津々、応募しました」
一団員として参加するつもりだった岡村さん。しかし、その人一倍ユニークなキャリアが航海のなかで大ブレイクすることになりました。
「講演を行ってくださる先生の1人が、急用のため寄港先で急遽、下船してしまったのです。そこで、代役として私が指名され、船長さんと対談することになりました」
太平洋を横断した経験談や、日本に帰ってからの経緯など、話題には事欠かない岡村さん。当然のことながら講演は参加者を魅了し、次年度の「若人の船」には正式に講師として乗ることになってしまいました。また、この航海で岡村さん自身も今後の塾運営に関する大きなヒントを得たといいます。
 |
B&G若人の船の一コマ
(中央が岡村さん) |
「私は、キャンプを中心にした野外活動教育を目指していたのですが、B&G『若人の船』と出会うことで、こんな方法もあるのだと目からウロコが出る思いになりました。ですから、いつかは私も同じような発想で船を使った活動をしてみたいと考えました」
航海から戻って4月に入ると、いよいよ待望の塾が始まりました。平日の夜は学習塾、週末や夏休みなどにはキャンプやヨットなどの野外活動メニューを展開します。学習塾の講師は、結婚したばかりの奥さんが国語を担当。1級建築士の資格を持っている岡村さんは、得意の数学を受け持ちました。
「家内も、私と同じようにレクリエーション指導員の資格を持っていて、ボランティアで子どもたちのキャンプの世話をしていました。2人で同じ価値観を持って塾を始めることができて、とても良かったと思います」
初年度の塾生は12名。この数では十分に生計が立てられないので、岡村さんは建築の図面を引いて生活費を工面しました。以前、建設会社に入るとき、「3年間は現場監督を経験しろ」、そして「一級建築士の資格を取るまでは会社を辞めるな。資格を取れば生きることへの自信が身につく」と、社長さんから言われましたが、まさにその言葉どおり、辛かった時期に得た1級建築士の資格が岡村さんの新生活を支えてくれました。前回でも述べましたが、この社長さんのことを岡村さんは今でも尊敬してやまないそうです。
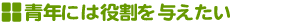
12名と数こそ少なかったものの、岡村さんが目指す事業のスタートにとっては理想ともいえる子どもたちが塾に集まってくれました。
「子どもたちの親は、皆さん口をそろえて『我が子は、もやしっ子だけにはなってもらいたくない』と言って塾の門を叩いてくれました。最近は、『どうして、わざわざ暑い最中に外に出てキャンプをしなければならないの?』などと言われてしまうケースが少なくありませんし、キャンプの参加料金にしても安く設定すると、むしろ集まりが芳しくありません。それに比べ、塾を開いた昭和59年当時の親たちは、なぜキャンプなどの野外活動が大切なのかを良く理解していました。つまり、彼ら自身が子どもの頃に川で魚を獲ったり、汗をかきながら山を登ったりした経験を持っていたわけです。そのような親を持つ子どもたちばかりが集まってくれたので、塾のスタートとしては助かりました」
 塾の評判はしだいに高まり、運営に自信をつけた岡村さんは平成4年になると、ついにこれまで心の中に温めておいた船を使った事業に着手します。 塾の評判はしだいに高まり、運営に自信をつけた岡村さんは平成4年になると、ついにこれまで心の中に温めておいた船を使った事業に着手します。
「どう考えても、B&G財団さんのように船をチャーターするような大掛かりなことはできません。そこで考えたのが定期便の客室を利用して沖縄へ行くことでした。これなら普通の料金で乗れますし、定期便ですから保険や運行管理の責任も船会社が持ってくれます」
「少年練習船」という名で始められたこの事業(現在は『ジュニア洋上スクール』に改名)は6泊7日の日程が組まれ、寄港地の沖縄では当時のB&G本部海洋センター(現在のマリンピアザオキナワ)に3泊して、さまざまな野外活動が行われました。
「第1回目の『少年練習船』では、まだ運営のノウハウをしっかり持っていなかったために150万円の赤字を出してしまいましたが、予想を反して200人もの子どもが集まってくれて大盛況となりました」
そこで問題になったのは、誰が子どもたちの面倒を見るかということでしたが、岡村さんは構想の段階から、子どもの面倒は高校生や大学生のボランティアにしてもらうと決めていました。塾を始めて、すでに何年も経過していましたから、塾を出た子どもたちは高校や大学に進学していました。彼らは野外活動を一通りは経験していましたから、立派な戦力だったのです。
「塾に通った子どもたちが、高校や大学に進学したために野外活動から遠のいてしまったら、もったいない話です。また、単に手伝いではなく、ボランティアで参加してもらうことで、彼らに社会参加の機会を与えたかったのです」
 |
| ボランティアで協力する岡村塾の卒業生たち |
さっそく、大学生になっていた塾のOBたちが名乗りを挙げてくれ、岡村さんも彼らに大きな期待を寄せました。
「航海に出て、この試みが大正解だったことが分かりました。親と同じような年齢の大人ではなく、もっと身近な年齢の大学生が班長といった直接的な立場の指導者になると、子どもたちは彼らに憧れを抱きやすくなり、指導している側の苦労も伝わりやすくなるのです」
その効果があって、翌年にはリピーターで参加した子どもたちが20%にも達しました。また、高校生や大学生の多くは、学校を卒業すると思うようにボランティアで参加できなくなりますから、毎年のように入れ替えが生じます。その新陳代謝のおかげで事業のマンネリを防ぐことができているそうです。
「大勢の子どもたちの面倒を見るわけですから、ボランティアのスタッフは大変です。しかし、20歳ぐらいの青年たちでも、一定の役割や責任を与えてあげると、それなりに指導者らしい顔つきになっていくものです。つまり、どんな人間でも自分の役割が自覚できると、それなりの立派さが身につくのです。私としては、その機会を彼らに作ってあげたい、そう思うようになっていきました」
「少年練習船」を始めた翌年、さらに岡村さんは事業の手を広げます。というのも、それまではベニア板で 作ったOPヨットを海岸に並べてセーリングを子どもたちに教えていたのですが、台風でヨットが流されてしまいました。途方に暮れた岡村さんでしたが、B&G財団の職員からアドバイスを受け、B&G海洋クラブの申請をしたところ、認可を受けることができたのです。
「すでに、ヨットを保管するための土地を海岸に買っていたので、B&G海洋クラブの名をいただいたことを契機に1000万円ほど借金をして合宿所を作りました」
これで本格的にヨットの授業ができるようになったほか、岡村さんはキャンプやウォーキングなど、さまざまな野外活動を展開。やがて、県内外で「教育の岡村」という評判が立ち始め、塾の事業も順調に進んでいきました。
|




