

 |
|||
 |
|||


伊賀市立大山田小学校/
伊賀市大山田B&G海洋センター
伊賀市立大山田小学校:
平成16年の市町村合併によって伊賀市が誕生したことを受けて、翌、平成17年4月に開校。地域や命を大切にする教育方針を掲げ、平成18年度から「水に賢い子どもを育む年間型活動プログラム」を4年生の「総合的な学習の時間」に導入している。
伊賀市大山田B&G海洋センター:
旧大山田村に昭和63年開設(体育館、プール、艇庫)。伊賀市政に移行した後も地域の社会体育事業を担う拠点になっており、公民館も隣接されている。
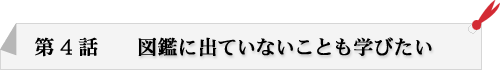

![]()
4年生の「総合的な学習の時間」を活用しながら、7年続けて水プロを展開している大山田小学校。第4話以降では、今年2月に開催された第7回B&G全国教育長会議で事例報告を行うなど、水プロ授業に深い関心を寄せている川端 清校長先生にプログラム導入の効果などについて語っていただきます。
![]()

大山田小学校が水プロ授業を始めてから、三代目の校長となる川端先生。同校に赴任した際、川端先生の目に水プロはどのように映ったのでしょうか。
私の家も、少しほどですが地元で農業を営んでいます。かつては、子どもたちが素足で駈けずり回っていた里ではありましたが、いつしか道が整備され、農業も機械化が進んで地域の景色がしだいに変わっていきました。
そんななかで、「危険だから川には近づくな」、「山に入ったら危ない」といった風潮が広まり、それに学校も応じざるを得ない状況になっていきました。そうなると、どうしても囲い込み的な発想の授業になりがちで、五感を働かせた自然体験を子どもたちにさせてあげることが難しくなっていきました。
私が子どもの頃は、川原で転んでケガをするといった経験を通じて、知らないうちに足の指先で石ころを確かめながら川に入るようになっていきました。そのような知恵のないまま、いきなり川に入れば浮き石で転んで流されてしまい、場合によっては深みにはまってしまいます。
それはとっさの出来事であり、気がついたときには溺れてしまっているということもあり得ます。そのような水辺の危険を学ぶことも含め、子どもたちにとって水プロはとても貴重な体験授業になっていると思います。
![]()
水プロでは、最初に水辺の安全を学ぶカリキュラムになっていますが、実際に地元の水辺に出てからは、どのような活動をしながらどのようなことを学んでいくか、それぞれの学校で考えることになっています。大山田小学校でも近隣の川に出て授業が進められましたが、そこからどのような成果を得ることができたでしょうか。


はっきり言えることは、学校の外に出て自然の動植物に触ってみることがとても良い体験であるということです。川に棲息する生き物のヌルヌルした感触などは、コンピューターで検索したり図鑑を見たりしただけでは分かりませんし、どうしたらペットボトルの仕掛けに魚を追い込むことができるかといった工夫や努力は現場を体験するなかで養われます。
パソコンが普及した昨今、バーチャル化は東京だけでなくここでも起きています。情報がたくさんあって簡単に調べることができるので、さまざまなことについて家から出ないまま分かったつもりになってしまいがちですが、水プロは実体験の大切さを私たちに伝えてくれています。
また、こうした実体験を通じて子どもたちはさまざまなことに関心を寄せていきます。私が校長に赴任してからも、水プロの内容は実にさまざまな方向に発展しており、毎年のように進化しています。
たとえば、後輩たちに残してあげたいと言って校庭に果樹園を作り、地域の川原で発掘された古代生物の化石に関心を示し、同類のものが琵琶湖博物館にあることを知って、地元の川と琵琶湖とのつながりを探求しています。
水プロを通じて川原の化石に目を向け、そこで自分たちが生まれ育った土地を知ることに発展したというわけです。また、教室ではなく現地に出向いてワイワイしながら調べていくので、仲間同士のコミュニケーションも深まります。人と人とのつながりの大切さも学べるのでとても貴重な授業になっています。
学校の外に出て行う水プロの特徴について語っていただいた川端校長先生。次回は、おもに人間教育の観点から水プロを語っていただきます。(※続きます)