

 |
|||
 |
|||


伊賀市立大山田小学校/
伊賀市大山田B&G海洋センター
伊賀市立大山田小学校:
平成16年の市町村合併によって伊賀市が誕生したことを受けて、翌、平成17年4月に開校。地域や命を大切にする教育方針を掲げ、平成18年度から「水に賢い子どもを育む年間型活動プログラム」を4年生の「総合的な学習の時間」に導入している。
伊賀市大山田B&G海洋センター:
旧大山田村に昭和63年開設(体育館、プール、艇庫)。伊賀市政に移行した後も地域の社会体育事業を担う拠点になっており、公民館も隣接されている。
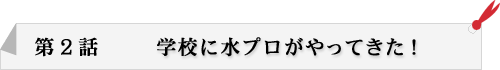
![]()


B&G「水辺の活動推進セミナー」に参加した学校の先生方から一定の評価を受けた、「水に賢い子どもを育む年間型活動プログラム」(以下、水プロ)。セミナー開催後、さっそく、大山田小学校が平成18年度から水プロを授業で行うことを決めました。
「水プロの良さを理解していただいた後は、地域の自然や文化に則して実際にどのような授業を組んだらいいのか、中身を考える作業が待っていました」(伊賀市教育委員会 児玉泰清 副参事)
検討の結果、大山田小学校は4年生の「総合的な学習の時間」に水プロを組み入れることを決定。児玉さんたち海洋センターのスタッフは、新学期のスタートに合わせて4年生の担任の先生とミーティングを開いて年間スケジュールを固めていきました。
「まずは、子どもたちがどれだけ地元の水辺について知っているのかを探ることから入り、続いて水辺の安全教育やマリンスポーツ体験といった基本的なメニューを行いながら、地域の水辺の文化や歴史、生物観察などを通じて自ら調べ学ぶ『総合的な学習の時間』に則った授業内容を模索していきました」
![]()
大山田小学校を含め、伊賀市の小学校では「総合的な学習の時間」で人権の大切さを学んでいました。そのため、水プロでも地域の人々が手を携えながら暮していることを学ぶ内容が盛り込まれました。
「近隣の山々から流れ出た川の水は、地元の人たちはもちろんのこと下流で暮す人々の生活も支えています。水プロでは、たくさんの人を潤す大切な水がどのようにして使われているのか、地域の人たちに講師をお願いしながら学んでいくことになりました」

とはいえ、いきなり講師をお願いしても引き受けてくれる人はなかなか出てきません。水プロを始めた当初は、水に関わる行政の担当職員に講師をお願いして住民参加の下地をつくっていきました。
「水プロを導入する際、最初は行政に協力を求めると上手くいくと思います。そのなかから、やがて地域の人たちが『それなら自分にもできる』と手を上げてくれると思います」
大山田小学校の場合は、保護者会が中心になって地域に声を掛け、徐々に川や水田の歴史、文化に詳しい人を探していきました。
![]()

実際に水プロが始まると、多くの子どもたちが喜びの声を上げました。川や山に行って自然に触れ合うことが、普段の学校生活にはない新鮮な体験だったからでした。
「どの地方でも同じことが言えると思いますが、最近の子どもたちの多くは川や山でなかなか遊ぼうとしません。ですから、川に行ってどんな生き物が棲んでいるのか探したり、川の水がどのようにして水田に運ばれたりしているのか調べたりすることにとても興味を示してくれました」
春に水辺の安全学習を行い、夏にかけてマリンスポーツを楽しみ、川に出で生き物の生態を学んだ子どもたち。秋になる頃には、地域を潤す川がどこから流れてきているか知りたくなって水源地の山を登り、その水をどのようにして生活に使うのか知りたくなって上下水道施設を見学。そして、きれいな水を守りたいという意識が芽生えて清掃工場を見学するなど、行政担当者や地域の人たちに講師をお願いしながら、年間を通じてさまざまな授業が展開されていきました。
「私たち海洋センターは、水辺の安全教育やマリンスポーツ体験などでは先導的な役割を担いましたが、地域に出て学ぶ体験学習についてはメニューを提案する程度で、具体的な内容に関しては担任の先生方と子どもたちが話し合って決めていきました」
川で遊んだことをきっかけに、きれいな水をどうやって守ったらいいのか考えるようになった子どもたち。水道施設や清掃工場を見学したいと声を上げたのは子どもたちでした。大山田小学校の水プロ授業は、先生と子どもたちが意見を交わしながら進んでいきました。(※続きます)