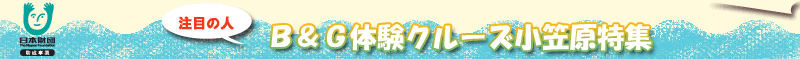

今回の注目の人では、組リーダー4名、ボランティアリーダー4名、ジュニアボランティアリーダー3名の皆さんのインタビューを、5回に分けてご紹介していきます。
※インタビューは帰港前日(第5日目)に行っています。
※各人の肩書き等は3月末日現在のものです。
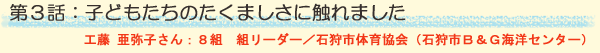
 ■ 今回のクルーズに参加した動機をお聞かせください。
■ 今回のクルーズに参加した動機をお聞かせください。
私は石狩市体育協会の職員として8年間、地元の海洋センターに勤務しています。一昨年には沖縄の指導者養成研修を受けてアドバンストインストラクターになりましたが、この資格を活かしたいと思ってクルーズの組リーダー募集に手をあげました。
私にとって、沖縄の研修はたいへん貴重な体験でした。マリンスポーツの勉強もさることながら、日常的なルールやマナーの徹底を通じて、人づきあいの基本を再認識することができたからです。クルーズにも同様の目的がありますから、そのような教えを今度は自分が子どもたちに伝える番が来たと思いました。
■ クルーズを振り返って、組リーダーの仕事はいかがでしたか。まず、500名近い子どもの命を預かったという大きなプレッシャーを感じました。そのため、普段ならさほど気に留めない子ども同士のふざけあいにも気を配るように心掛けました。船の上では、ちょっとしたことが大きな事故につながる場合もあるからです。
もっとも、乗船してからずっと緊張していたためか、クルーズ初日は子どもたちと一緒に私も船酔いしてしまいました。ですから、船酔いで心細い思いをしている子どもたちの気持ちはよく分かりました。
 ■ クルーズで一番楽しかったことは何ですか。
■ クルーズで一番楽しかったことは何ですか。
最初は、こちらが話しかけても目を逸らす子もいましたが、クルーズが進むにつれて子どもたちがいろいろ私に話しかけてくれるようになっていきました。このことが一番うれしかったです。
聞いてくることは、「リーダーって何歳?」、「結婚しているの?」、「彼氏はいるの?」といった個人的なことへの質問が多く、親しくなった大人に対して子どもたちが強い好奇心を抱くことがうかがえました。
■ 振り返って、工藤さん自身がクルーズで得たものは何ですか。班長や部屋長は、使命感を持って仕事をこなしてくれました。クルーズに限らず、どんなことでも何かの役目を与えて期待してあげれば、それなりに子どもたちは動いてくれるのではないでしょうか。そんな子どもたちの内面的なたくまさしを見て取れたことは、大きな糧になりました。
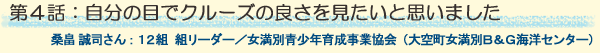
 ■ 現在、どのような仕事をされていますか。
■ 現在、どのような仕事をされていますか。
昨年の春、女満別青少年育成事業協会に就職し、地元の海洋センターに配属。夏には沖縄で指導者養成研修を受け、アドバンスト・インストラクターの資格を取りました。
■ 今回のクルーズに参加した動機は何ですか。海洋センターに勤務することになってB&G財団の事業をいろいろ勉強するなかで、小笠原クルーズに目が止まりました。全国から集まった500名近い子どもたちを、どのようにまとめながら航海するのか知りたくなったのです。
海洋センターの仕事に就く前、私は学校の臨時教員をしていました。学校では1年という長い目でクラスの運営を考えましたが、クルーズでは6日間という短い間に大勢の子どもたちと信頼関係を築かねばなりません。そのため、どうしたらこのような事業ができるのか、元教員の立場からクルーズの運営に興味が湧いたのです。
また、予備知識を得ようと事前に前回のクルーズを記録したDVDを何度も見ましたが、そのなかで子たちがしっかり活動しているので、ますます自分の目でクルーズの現場を見て体験したいと思いました。
■ 実際に組リーダーを担当してみて、どのような感想を持ちましたか。短期間でどれだけ子どもたちと信頼関係を作ることができるか、自分なりにいろいろ努力しましたが、実際の現場ではなかなか思うようにはいきませんでした。クルーズ後半に入ってようやく組全体がまとまってきましたが、それでも難しさを感じています。
しかし、クルーズの運営そのものについては実際にこの目で見て体験できたので、たいへん有意義でした。スムーズに進む入念なプログラムにも感心しましたが、あいさつや身だしなみといった日常的なマナーやルールをしっかり指導し、それを通じて全体がまとまっていくことが分かって大いに勉強になりました。
 ■ クルーズのなかで楽しかったこと、うれしかったことは何ですか。
■ クルーズのなかで楽しかったこと、うれしかったことは何ですか。
寄港地活動で子どもたちと海に入って、一緒に笑って楽しむことができました。このとき、「ここまで仲良くなれたんだな」と実感することができました。
■ 子どもたちから教えられたことはありますか。子どもたちは、ボーッとしているようでも大人の行動はよく見ています。私が考え事をしていれば傍に寄ってきて心配そうに顔を覗き込むし、リーダー同士で何か相談していても、やはり何人かの子が心配そうに寄ってきます。子どもは、大人の気持ちを覚る名人だと思います。
■ クルーズをどのように締めくくりたいと思いますか。子どもたちについては、最後に笑顔で船を下りることができればいいかなと思っています。私自身については、長年にわたって培われたクルーズ運営のノウハウの一端に触れることができて、とても参考になりました。今回の貴重な経験を今後の仕事に活かしていきたいと思います。

