

 |
|||
 |
|||


柳川市:平成17年に周辺三市町が合併して誕生。人口は約7万7千人。有明海に面する水郷の城下町として知られ、ゆっくりと水路を旅する「ドンコ舟」の川下りが有名。市内には昭和56年(1981年)に開設された柳川市大和B&G海洋センター(体育館・艇庫)があって活発な活動を展開している。
石田宝蔵(いしだ ほうぞう)市長:昭和25年(1950年)、柳川市生まれ。旧大和町職員を経て平成6年から同町町長、平成17年からは新生柳川市市長に就任。市長就任後は、平成18年にB&G「地域海洋センターサポート21」審査委員長、ならびにB&G指導者養成事業・研修修了記念講話の講師を務める。水郷の利を活かして、市内に「やまと競艇学校」を誘致したことでも知られる。
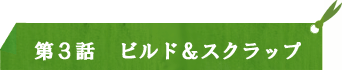

市長:普通に考えたら、プールなら水泳、体育館なら球技や武道、体操といったように、海洋センター施設の活動メニューはだいたい限られると思います。しかし、「地域海洋センターサポート21」といったコンテストを開くことで、施設利用のさらなる発展性が見えてきます。
たとえば、プールでOPヨットやカヌーの体験試乗を行うアイデアなどは、“プールは泳ぐ場所である”という固定観念を捨てなければ生まれません。日常的な活動の中ではなかなか思いつきませんが、このようなコンテストを開くことで、そんなユニークな発想もいろいろ生まれます。
また、コンテストではお年寄りを対象にした案も目立ちました。高齢化社会の到来という時代の流れを感じるのと同時に、海洋センター施設が地域コミュニティの拠点になっていることを再認識しました。
 「地域海洋センターサポート21」審査委員長を務めた石田市長(左)と、「ウォークラリー」でドリーム賞に選ばれた北海道積丹町の丹場さん
「地域海洋センターサポート21」審査委員長を務めた石田市長(左)と、「ウォークラリー」でドリーム賞に選ばれた北海道積丹町の丹場さん市長:子どもたちがゲーム感覚でカヌーの川下りを楽しむ案も高い評価を得ましたが、「ウォークラリー」は、すでにあるウォーキングを活用できる点や、健康増進で医療費の低減に貢献できる点、グリーンランド事業としてPRできる点が注目されました。
ただ、いくらユニークな案が生まれても実際に行われなければ何の意味もありません。ドリーム賞に選ばれたウォークラリーは実現されていると聞きましたが、コンテストでいろいろ提案されたことが、今後どのような発展を見せるのか期待しています。
市長:おっしゃる通り、どんな職場でも新しい仕事を取り入れたら、その分だけ忙しくなるものです。そのため、昔からスクラップ&ビルドという考え方がありました。つまり、余計になった古いものを壊して新しいものを作るという発想です。
ところが、この発想では現代社会のスピードについていけません。いまはビルド&スクラップで対応していく必要があります。現代社会では、黙っていても仕事は増える一方です。そのなかで、何を捨てるのかという作業をちゃんとしなければならないというわけです。それを怠ると、仕事に追われるだけになってしまいます。
いろいろなところで、「忙しい」とか「仕事が大変だ」という声を聞きますが、忙しさを自分たちでつくってしまっているケースも少なくありません。職場でミーティングしながら仕事を整理することが大切です。
第一、古いものも新しいものも一色単にしていたら、総花的になって仕事の根本が見えなくなってしまいます。新しい仕事が生まれるなかで、古いものをスクラップしていかないと全部が中途半端になってメリハリがなくなってしまうのです。2つ3つの仕事にウエイトを置き、それを何年か重点的に続けてみようといった試みが必要です。
そのような発想を持てば、「地域海洋センターサポート21」で考案された新事業も積極的にできるのではないでしょうか。仕事にメリハリをつけることができる職員は有能であると思います。 (※続きます)