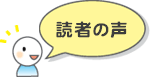
今日NHKのTVで知りました。
私の祖父も滋賀県の出身、といっても蒲生郡の方ですが…気になって拝見しました。 農業は大変な仕事、若い方が地元の良さを再発見していく姿に感動、嬉しくなりました。
市長さんも針江の方と知りこれからの取り組みがとても楽しみです。
以前から水には興味があったのでいつかお尋ねしたいと思いました。
ありがとうございました。
―8月25日書き込みの方―
 |
|||
 |
|||

 針江地区の水田を見学する人々。地元では「針江生水の郷委員会」を立ち上げ、地域住民が交代でボランティアの案内役を務めています
針江地区の水田を見学する人々。地元では「針江生水の郷委員会」を立ち上げ、地域住民が交代でボランティアの案内役を務めています
 高島市 海東英和市長:昭和35年(1960年)、高島市新旭町針江に生まれる。旧新旭町職員、同町議会議員、同町長を経て平成17年(2005年)、市町村合併によって誕生した高島市の初代市長に就任。
高島市 海東英和市長:昭和35年(1960年)、高島市新旭町針江に生まれる。旧新旭町職員、同町議会議員、同町長を経て平成17年(2005年)、市町村合併によって誕生した高島市の初代市長に就任。 取材時、針江地区では田植えを控えて豊富な湧水が田に送られていました
取材時、針江地区では田植えを控えて豊富な湧水が田に送られていました
「雄大な山や海も自然ならば、さまざまな生き物と上手に共存している人里の姿も自然の一部と見るべきです。本来、人間も動物も、そして植物も、お互いに自然の一部を担う存在です。川端の水文化を目にすることで、そんな物の考え方を知ることができると思います」
環境省がエコツーリズムのモデル地域を選定する際、高島市の海東市長は川端の水文化を関係各所に自薦して回りました。とかくGDPなどの経済的な尺度で、その地域の豊かさが比較されがちですが、暮らしぶりの幸福度を計るには、もっと違った尺度もあるのだということを多くの人に知ってもらいたかったのです。
「GDPや納税額といった一律の尺度だけでなく、もっと地域が持つ多様性に目を配って欲しいと思います。そのような尺度がなければ、本来、日本の農村が持っている豊かさを伝えることはできず、一律の尺度のうえで見放されていくばかりになってしまいます」
 針江地区の家並み。昔から、焼いて黒くなった杉板が家の外壁に使われています
針江地区の家並み。昔から、焼いて黒くなった杉板が家の外壁に使われています
より人の手が加えられた米はおいしくなります。おいしい米が広まれば、産地である地元に人々の目が集まり、出荷が増えて収益が上がれば、より丹念な米づくりができるという好循環が生まれます。
「地元の水を守れば、田から琵琶湖に向かう水もきれいになります。琵琶湖の水は京阪神地域の水ガメですから、京都や大阪など都会の人々に私たちの米を食べてもらうことは、琵琶湖の水をきれいにすることにつながります。このように、水を通じた良き関係を都会の皆さんと築いていきたいと思います」
そこには、高島市がスローガンに掲げている「お互いさま」と「おかげさま」の人間関係がよく現れています。
高島市内の山間部に展開する棚田は、昔ながらの石堤で仕切られていますが、ここに強い農薬を撒くと太い根で石堤を支えている雑草まで枯れてしまいます。そこで、棚田を持つ人たちは農薬を撒くのをやめ、人力で丹念に雑草を刈るようになりました。きれいな水を守り、おいしい米をつくることが、我が故郷を支える力になるということが、着々と浸透しています。
 葦が群生する琵琶湖でも最大級の湿地帯が針江地区に隣接しており、さまざまな動植物の宝庫になっています
葦が群生する琵琶湖でも最大級の湿地帯が針江地区に隣接しており、さまざまな動植物の宝庫になっています
「景勝地のなかには、多くの人が勝手に足を踏み入れて自然が荒らされてしまった場所もありますし、逆に、貴重な自然だからと言って人を締め出してしまう場所もあります。そうではなく、自然の回復力を超えない範囲でなるべく多くの人にその土地のすばらしさを体験してもらうよう、地元の人たちが工夫を凝らす必要があると思います」
川端の水文化の場合も、住民がなにも方策を考えなかったら、水路にゴミを落とされたり、場合によっては訪れた人たちが勝手に人の家の台所まで入り込んで荒らしてしまったりしたでしょう。また、だからといって地域全体を立ち入り禁止にしたら、閉ざされた里になって住民の活気が失われてしまいます。
 湿地帯の外れには小さな漁港があり、昔ながらの鮒漁が続けられています
湿地帯の外れには小さな漁港があり、昔ながらの鮒漁が続けられていますそこで思いついたのが、料金をいただいて住民が交代でガイドを行うエコツアーだったのですが、この料金は見学料ではなく水文化の保全に使う協力金になっています。エコツアーに参加した人たちは、単に見学するのではなく、ガイドと一緒に周辺の自然を散策しながら湧水を飲み、顔なども洗っていただいています。
つまり、エコツアーを通じて住民とともに周辺地域の自然を享受してもらう、双方向の関係を目指したのです。これは、協力金を払って森や山に入った人は、地元の人と同じように自然を満喫することができるという、北欧などで見られる自然享受権の発想と同じです。川端のエコツアー料金は、環境を整えておくための経費に充てられますから、川端や水路、町並みなどが荒廃してしまうことはないと思います」
 川端を潤した湧水は水路を通じて田に送られた後、琵琶湖へと向かいます
川端を潤した湧水は水路を通じて田に送られた後、琵琶湖へと向かいます「川端や里山は高島市の個性ですから、その大切さを住民に知ってもらう努力が必要です。ただし、市内各地域で高齢化が進んでいますから、将来的には地元の努力だけで美しい自然を守り抜くことはできないと思います。ですから、これからは『お互いさま』と『おかげさま』の人間関係を都会の人たちと結びながら、里を大切にしていく発想が求められます」
川端の水路は、年に何度となく地元の人たちが総出で掃除していますが、最近では「ここから、1400万人(京阪神地区)の水ガメへきれいな水を送ろう」というキャッチフレーズで、夏場に「藻狩りツアー」が企画されるようになりました。
 平成15年にリニューアルオープンした高島市高島B&G海洋センター。体育館、プールのほか、ボートハウスも整備されています
平成15年にリニューアルオープンした高島市高島B&G海洋センター。体育館、プールのほか、ボートハウスも整備されています
「都会から来た人たちが、カマを手に私たちと一緒に汗をかいてくれることの意味は大きいと思います。参加した人たちとは、川端の水文化を大切に思う良き友として末永く交流していけるのではないかと思います」(針江生水の郷委員会:美濃部武彦会長)
このように体験型のプログラムが多くの人に受け入れられるようになると、今後は市内2カ所にあるB&G海洋センターの利用価値も高まっていくであろうと、海東市長は考えています。
 高島市今津B&G海洋センターを拠点に活動を展開しているB&G今津海洋クラブ。夏場はカヌーで琵琶湖に繰り出します
高島市今津B&G海洋センターを拠点に活動を展開しているB&G今津海洋クラブ。夏場はカヌーで琵琶湖に繰り出します
水に慣れ親しむ子どもたちが増え、お互いに交流を深めていくことは、川端のような水文化を残していくうえで大きな力になるはずであると、海東市長は語っていました。(完)