

 |
|||
 |
|||


1948年3月、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。中学時代にサーフィンと出会い、大学を中退して渡米し、サーフボードの製作を勉強。帰国後、サーフボード製作に携わりながら、1969年の全日本サーフィン選手権大会で優勝。ウインドサーフィンにも興味を持ち、大会DJやプロデューサーとして活躍。1989年には、湘南の海岸で多数のマリンイベントが開催された「サーフ90」の企画に携わり、その経験をもとに1993年、通年型の「湘南ひらつかビーチクラブ」ならびに「ビーチパーク」を設立。現在、同様のクラブを全国6ヵ所で展開中。著書も多数あり、最近では「家族で楽しむ、ドジ井坂の海遊び学校」(マリン企画)を出版。
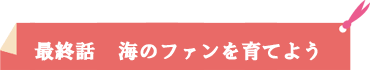
 江ノ島ビーチクラブは海水浴場開設のため7〜8月はお休み。9月がビーチクラブの海開きで、翌年の6月まで海で遊びます
江ノ島ビーチクラブは海水浴場開設のため7〜8月はお休み。9月がビーチクラブの海開きで、翌年の6月まで海で遊びます「ひらつかビーチクラブ」を結成して間もなく、ドジ井坂さんに子どもが生まれました。
「妻は、泳ぎはあまり得意ではありませんでした。そのため、彼女は子どもをお風呂に入れると、顔にお湯がかからないように注意しながら頭を洗っていました。
我が子が2歳になってからは、私もお風呂に入れるようになりましたが、その際、水と親しめるように頭から湯をかけるとすごく嫌がるのでとてもショックを受けました」
自分が親しむマリンスポーツを、子どもにも楽しませてあげたい。そう考えていたドジさんにとって、我が子の反応は辛いものでした。
「水って楽しいんだよ」と言いながら、何度も一緒に水遊びを試みるドジさん。しかし、そんな努力をすればするほど我が子は水から遠ざかっていきました。4歳になる頃には、サーフィンを教えてあげようとしましたが、一向にドジさんの言うことは聞いてくれません。
 逗子では一般参加者が経験を積んで、子どもたちにウインドサーフィンやサーフィンの体験レッスンをするようになりました
逗子では一般参加者が経験を積んで、子どもたちにウインドサーフィンやサーフィンの体験レッスンをするようになりました
「そのとき、ハッと自分の経験を思い出しました。私の父は陸上競技のオリンピック・コーチだったため、子どもの頃の私は、陸上のことになるといつも父から細かい指導を受けていたのです。陸上競技自体は嫌いではありませんでしたが、あまりにも父が陸上競技にこだわるため、次第に私はうんざりするようになっていきました」
同じようなケースの子どもたちを、ヨットやウインドサーフィンといったマリンスポーツ競技においてもよく見かけると、ドジさんは言います。
「親は当然のように思っていますが、1つの種目しかやらせてもらえない子どもにとっては、とても大きなストレスになる場合が多いのです。せっかく海に連れて来てもらっても、ほかの遊びをさせてもらえないのであれば、いくら親が好きな種目でも子どもにとっては強制させられていると感じてしまいます」
 東京羽田は1年中いろいろな魚貝類料理を楽しめる豊な海です。来年から「大森ふるさとの浜公園」で定例活動が始まる予定です
東京羽田は1年中いろいろな魚貝類料理を楽しめる豊な海です。来年から「大森ふるさとの浜公園」で定例活動が始まる予定です子どもの頃の自分を思い出し、我に帰ったドジさんは一計を案じました。
「親である自分がサーフィンを教えようとするから、子どもがプレッシャーを感じてしまうのだろうと思い、私と仲の良い友だちが私の子を、そして私が彼の子の世話をしながら一緒に遊ぶ感覚でサーフィンをしてみたのです」
親同士がお互いの子の世話する、この試みは大成功。これをきっかけにドジさんの子は海で遊ぶことが好きになり、たくさんの親子がやって来るビーチクラブに通うようになっていきました。
「我が子を家庭から離して地域に育ててもらうことも、ときには大切です。親以外の大人と関わることは、社会勉強の第一歩になるはずです。その意味からも、いろいろな親子が参加するビーチクラブの存在は、私にとってもありがたいものでした」
 東阿南ビーチクラブでは、徳島県阿南市北の脇海岸で毎月第1土曜日に定例活動を行っています
東阿南ビーチクラブでは、徳島県阿南市北の脇海岸で毎月第1土曜日に定例活動を行っていますドジさんの親子関係も救ってくれたビーチクラブ。その活動に国土交通省も注目し、2002年に同省港湾局が立ち上げた「新たな海辺の文化創造研究会」のなかで、「ビーチスポーツ研究会」という部会が誕生。その委員として、ドジさんは江ノ島の海岸で社会実験イベントをコーディネートしながら、「ビーチクラブ型海岸活動の提言」をまとめました。
こうした経緯を踏まえて、2004年には江ノ島と逗子にビーチクラブが誕生。その後、千葉県鴨川市や徳島県阿南市、東京都大田区羽田などにも同様のクラブ拠点が設立され、各地で年間を通したさまざまな海遊びが展開されるようになっていきました。
「江ノ島で国土交通省の社会実験イベントを実施した際、参加者からアンケートを集めてみると意外な回答が多いので驚きました。『ビーチで遊ぶイベントは、いつがいいか』という問いに対して、『5月』そして『9〜11月』と答えた人が大半を占め、『7、8月の夏場がいい』と答えた人は少数だったのです。
皆、『海水浴以外の海遊びだったら暑苦しい夏は避けたい。海遊びは夏以外でも楽しめる』と思ってくれたのです」
社会実験イベントに参加しただけで、多くの人が、海遊び=海水浴、海水浴=夏という固定観念を払拭した事実は、ドジさんの考えるビーチの通年利用を実証するものでした。海水浴だけでなく、年間を通じて多くの人が憩うビーチを実現したい。そう思いながら奮闘し続けてきた苦労が癒された出来事でした。
 鴨川ビーチクラブでは、千葉県鴨川市横渚千葉未来高等学校前の海岸で毎月第2日曜日に定例活動を行っています
鴨川ビーチクラブでは、千葉県鴨川市横渚千葉未来高等学校前の海岸で毎月第2日曜日に定例活動を行っています
国土交通省の社会実験イベントを契機にクラブが6カ所まで増えた現在、ドジさんは各クラブが地域におけるコミュニティ活動の場になるよう働きかけています。
「浜辺に年間を通じて海遊びが楽しめる環境を整えるためには、そこに暮す海好きの人たちの協力が必要です。今後は、いままでの活動で海好きになった人たちが核となって、クラブの活動を地域に根ざしたものに育てていってほしいのです。
そのため、現在、クラブ活動を通じてマリンスポーツはもちろん地域の海岸の自然に詳しくなった人たちに、「ビーチコーディネーター」の役を担ってもらう構想を進めています。彼らは、スポーツの専門家でもなければ自然を研究する学者でもありませんが、浜辺を管理する自治体とのパイプ役を務めながら、いろいろな海遊びを通じて地域の人々を海にいざないます」
ビーチコーディネーターを中心としたクラブの人たちの努力によって、より多くの海のファンが地域社会に増えていくことを楽しみしているドジさん。B&G地域海洋センター・クラブにも大きな期待を寄せています。
 誰でも気軽にマリンスポーツが学べるよう、ドジ井坂さんはさまざまなアイデア商品を開発しています。写真は自宅でもできるサーフィンのトレーニングキット。ボードに見立てたシートに足を置いて、波に乗るために必要な体重のかけ方や動作が気軽に練習できます。
誰でも気軽にマリンスポーツが学べるよう、ドジ井坂さんはさまざまなアイデア商品を開発しています。写真は自宅でもできるサーフィンのトレーニングキット。ボードに見立てたシートに足を置いて、波に乗るために必要な体重のかけ方や動作が気軽に練習できます。「さまざまな水辺のイベント、活動を展開しているB&G海洋センター・海洋クラブは、陸に目が向いた公共施設が多い我が国の現状のなかで、とても貴重な存在です。カヌーやOPディンギー、そしてウエットスーツといったハードを活用しながら海遊びを地域の親子に広め、より多くの海のファンを育てていただきたいと思います。
ウエットスーツを着れば夏でなくても水に入れるということを、どれだけの人が知っていることでしょう。皆、敷居が高いと感じてマリンスポーツの世界になかなか入り込めないでいるのです。
ですから、ビーチクラブやB&G海洋センター・海洋クラブが、ある程度は利用のルールをつくりながら、『そんなことはないよ。一緒に遊ぼうよ』と声をかけてあげる必要があるのです。地域によっては、ビーチクラブと海洋センターが情報を交換しながら活動をリンクしてもいいのではないかと思います」
それぞれの浜辺が異なる景色を持つように、全国各地に地域ならではのビーチ活動が花開くことを願っているドジ井坂さん。海辺に暮す人々が、口を揃えて「私の故郷は海です」と言える日が来ることを、楽しみにしているそうです。(※完)