

 |
|||
 |
|||


1948年3月、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。中学時代にサーフィンと出会い、大学を中退して渡米し、サーフボードの製作を勉強。帰国後、サーフボード製作に携わりながら、1969年の全日本サーフィン選手権大会で優勝。ウインドサーフィンにも興味を持ち、大会DJやプロデューサーとして活躍。1989年には、湘南の海岸で多数のマリンイベントが開催された「サーフ90」の企画に携わり、その経験をもとに1993年、通年型の「湘南ひらつかビーチクラブ」ならびに「ビーチパーク」を設立。現在、同様のクラブを全国6ヵ所で展開中。著書も多数あり、最近では「家族で楽しむ、ドジ井坂の海遊び学校」(マリン企画)を出版。
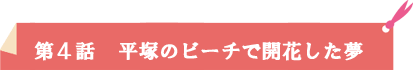
 安定の良いウッドデッキを使いながら、子どもにウインドサーフィンを教える「ひらつかビーチクラブ」のメンバーたち。奥にビーチバレーのコートが控えています
安定の良いウッドデッキを使いながら、子どもにウインドサーフィンを教える「ひらつかビーチクラブ」のメンバーたち。奥にビーチバレーのコートが控えています 海との共生をテーマに、年間を通じてさまざまな海遊びのイベントが繰り広げられた、神奈川県主催による「サーフ’90」。平塚地区の会場プロデューサーとして腕を振るったドジ井坂さんは、イベント終了後もビーチ活動の存続を求めて県や市と交渉を重ねていきました。
海遊びは夏場だけのものという思い込みをなんとか払拭し、欧米のようにあらゆる人がいつでも海と親しめる環境をつくりたかったのです。
「ちょうど、我が子が生まれたときのことでした。どうやって自分の子を育てていこうかといろいろ考え、最初は父親である私が個人的に水泳やサーフィン、ヨットなどを教えれば済むと思ったのですが、実はそれがあまり良くない結果を生んでしまうことに気がつきました。
自分の子だけがマリンスポーツに精を出していたら、子ども同士の社会のなかで我が子が孤立してしまう恐れがあるのです」
そうであるなら、大勢の子どもたちが年間を通じて海遊びを楽しむ環境をつくらねばなりません。しかし、ドジさんはとても高いハードルを感じていました。
「海遊びといえば夏場の海水浴だけが一般に広まってしまったためか、サーファーやヨットマンなどは特別なことをしている人たちであるという目で見られることが少なくありません。また、そのためもあってマリンスポーツのショップは玄人好みの高級品ばかりが目立ち、子どもたちが気軽に遊べる安価な入門品はなかなか見あたらないのです。このような状況が続くかぎり、たくさんの子どもがマリンスポーツを気軽に楽しむ時代はなかなか訪れません」

そんな思いもあって、「サーフ‘90」のビーチ活動存続に力を入れたドジさん。まずは、「サーフ‘90」の会場を残すよう平塚市に働きかけ、1991年に市営公共施設「湘南ひらつかビーチパーク」が誕生。
そこを拠点に「ひらつかビーチクラブ」を結成し、通年遊ぶ具体的な活動を展開し始めると、県や市も注目し始め、海水浴以外の海遊びで市民が楽しむことを理解するようになっていきました。
そして、1996年にはシャワールームや休憩室を備えた通年型の公共施設「湘南ひらつかビーチセンター」が誕生。長年、ドジさんが頭に描いてきた、年間を通じて海を楽しむ環境が整いました。
 ビーチでは、さまざまな遊びが楽しめます。足を蹴り上げて履いているビーチサンダルを飛ばす、「ビーチサンダル飛ばし」もその1つ。簡単なルールを決めて大会を開くだけで、子どもたちは夢中になります
ビーチでは、さまざまな遊びが楽しめます。足を蹴り上げて履いているビーチサンダルを飛ばす、「ビーチサンダル飛ばし」もその1つ。簡単なルールを決めて大会を開くだけで、子どもたちは夢中になります
ビーチクラブの活動を支えるため、ドジさんはメーカーやショップを回って、ディンギーやサーフボードなどの用具提供を呼びかけました。ビーチパークのハード面は平塚市によって整備されましたが、そこを利用するクラブの運営や道具に関しては自分たちで責任を持たねばならなかったのです。
「ショップに行ったら、『マニアのお客さんばかり相手にしないで、少しは地域の子どもたちの活動を手伝ってほしい。それができて、初めて一般から支持される専門店だと言えるはずだ』と訴え、20社ほどから道具に関するなんらかの協力を得ることができました」
ビーチパークのイベント用ヨット置き場には、ドジさん自らが提供した物も含めて数艇のカタマランディンギーやウインドサーフィンが並び、ビーチバレーのコートも通年利用できるように整備されました。
「ここで、ちょっとした教訓を得ることになりました。一年を通じて楽しめるビーチを目指すには、通年楽しんでくれる人が必要です。それまで日本にはビーチバレーの常設コートはなかったので、ビーチバレーを楽しむ元気な選手たちに声をかけて集まってもらったのです。すると、やがて全国のビーチバレー愛好者注目のビーチになりました。
しかし、多くの人たちにビーチバレーが一年中楽しめるビーチであることは認知してもらえましたが、一般の運動公園のようにスポーツ専用の場所になってしまい、誰もが気軽に楽しむ場所であるという雰囲気が薄れてしまいました。
第1話でも少し話しましたが、日本では専門家主導で一般が追従するパターンが多く、一般の人々が自主的にクラブをつくって気軽に遊べる環境を整えていく例は希少です。スポーツを地域に根ざすためには、誰が主体となって活動していくのかよく考えておく必要があります」
人が集まったのはビーチバレーのコートだけではありませんでした。イベント用ヨット置き場も、週末ごとに行われるディンギーやウインドサーフィンの無料体験セーリングで賑わうようになっていきました。
「ビーチパークにやってくる人なら誰にでも、『一度乗ってみない? 無料だよ』、『好きに動かしていいから、試してみない?』と声をかけ続けました。おもしろいもので、乗ってみたいと手を挙げた人に新艇を勧めると、決まって躊躇していましたが、キズがついたボロボロの中古艇であれば安心して乗ってくれました」
誰でも、新品にキズを付けたくはありません。まったくの初心者に敷居の高いマリンスポーツを教える際は、キズを付けても気にならない中古の道具を選んだほうが良いと、ドジさんは言います。

「ただし、いくらヨットやウインドサーフィンを勧めても、その人が勇気を出して乗ってくれないことには話になりません。実際、ディンギーを浜に出して『誰でも乗っていいんだよ』と手を差し伸べても、たいていの人が後ずさりしてしまいました。
興味があるから私の説明を聞いているのですが、海水浴以外の経験がないため、『よし、やってみよう』という勇気がなかなか出せないのです。最初の頃は、まるで野生の動物を餌付けしているような感覚でした。皆、食べてみたいけれど、怖いのです」
ここでドジさんは、集まった人たちにある共通した行動パターンがあることを知りました。
「本当に興味があって乗ってみたいと思った大人は、まず自分の子どもを乗せて様子をうかがい、それから自分がチャレンジしていました。どうしてなのか何人かに尋ねてみたところ、『これまで海に出たことがないから自信がないのです』と口を揃えていました。
前にも言いましたが、プールが学校に設置されて、『海は危険だから近づくな』という教育が始まって40余年。この間、我が国は本当に海と接したことのない人を無数に生んでしまったのです」
マリンスポーツを普及させるためには、大人たちへのアプローチも大切であることを知ったドジさん。その後、ひらつかビーチクラブでは家族ぐるみの活動が積極的に展開されていくことになりました。(※続きます)