

 |
|||
 |
|||


1948年3月、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。中学時代にサーフィンと出会い、大学を中退して渡米し、サーフボードの製作を勉強。帰国後、サーフボード製作に携わりながら、1969年の全日本サーフィン選手権大会で優勝。ウインドサーフィンにも興味を持ち、大会DJやプロデューサーとして活躍。1989年には、湘南の海岸で多数のマリンイベントが開催された「サーフ90」の企画に携わり、その経験をもとに1993年、通年型の「湘南ひらつかビーチクラブ」ならびに「ビーチパーク」を設立。現在、同様のクラブを全国6ヵ所で展開中。著書も多数あり、最近では「家族で楽しむ、ドジ井坂の海遊び学校」(マリン企画)を出版。
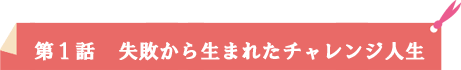
湘南の海辺で生まれ育ったドジ井坂さん(本名:井坂啓巳)。幼い頃から浜辺でよく遊び、中学生になると登山にも興味を抱いて、海と山の両方を楽しんで過ごしました。

「山に行った帰りに、気がつくと海辺に立ち寄っていましたから、どちらかと言えば海が好きだったのだと思います」
ある日、興味のあったアメリカンフットボールの本を洋書店で眺めていると、偶然にもサーフィンの本を発見。興味津々、ページをめくってみるとサーフボードの自作方法が紹介されていました。
「自分にもできそうだったので、さっそくこの本を手に入れ、ベニア板を使った簡単なボード作ってみました。そして、家の近くの浜で乗る練習をしていると、同じ仲間と出会うようになり、しだいにサーフィンにのめり込んでいきました」
とはいっても、まだサーフィンが日本に普及する以前の話です。そのため、仲間同士で技を磨き合うというよりも、ボートを使いながら皆で遊ぶといった雰囲気が強く、波がなければパドリングで烏帽子岩(茅ヶ崎海岸の沖にある岩場)まで漕いで行き、海賊ゴッコなどをして遊んでいたそうです。

「幸いにも、まだ私たちが子どもの頃は『海は危険だから近づくな』と注意される時代ではありませんでした。だから、このような遊びが自然にできたのだと思います。その後、プールが学校に設置されていくと、しだいに『海や川は危険』だと言われるようになり、臨海学校や遠泳大会などの行事が隅に追いやられてしまったことは残念でなりません。
いま、私はビーチクラブの活動を通じて30歳代の若いお父さん、お母さんたちと接してしますが、ほとんどの人は最初モジモジしていて、なかなかサーフボートなど海の遊び用具に触れようとしません。つまり、彼らの多くは子どもの頃に海に出て遊んだ経験がないのです。
現在の若い親でサーフィンやヨットなどを楽しんでいる人は、大人になってから海に出た人たちだと思います。彼らは世代の全体からすればきわめて少数ですから、本当に多くの日本人が海を知らないまま暮しているわけです。
私のような年配の世代にしてみれば、まさかと思ってしまいますが、日本人と海との接点がなくなってから、実は40年近くも経っているのです」
パドリングで遊ぶこともありましたが、ドジさんのサーフィンの腕は着実に上達。大学に入学するも1ヵ月で中退を決め、サーフィンの本場を知りたいとアメリカのカリフォルニアへ渡りました。
「大学の授業料を旅費に充て、『このお金は人生の勉強代にするから』と親に言って家を出ました。実際、カリフォルニアでは波乗りのスキルやサーフボード製作技術の取得に励みました」
その甲斐あって、帰国後の1969年に開催された初の全日本サーフィン選手権でみごと優勝。翌年にメキシコで開催される予定の世界選手権へ、日本代表として向かうことになりました。
「意気揚々と会場の浜に乗り込んでみたら、大会が開催されるような雰囲気は少しもありません。人に尋ねると、『来年に時期をずらし、オーストラリアで開催されることに変更された』と言うのです。当時は電子メールなんてありません。参加の問い合わせを手紙でやり取りしていたら、変更の知らせを手にするのが遅れてしまったのです」
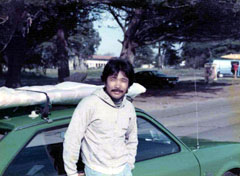
「翌年、オーストラリアに行っても、『ドジな日本のチャンピオンがやってきた!』、『君が、噂のドジな日本人か!』などと会う人ごとに話しかけられしまい、私も『まあ、そう呼ばれてもいいや』と思うようになりました。英語での会話が詰まったときには、ドジを踏んだことを話題に出すことで間が持つうえ、本名の啓巳(ひろみ)がよく女性に間違えられていたこともあったので、ドジという言葉の強い響きもまんざら悪いものではないと思ったのです」
新しい呼び名を持って、心機一転のドジさん。世界選手権の翌年、1970年には日本人のプロ選手として初めて招待されたハワイのプロ・アマ大会に出場し、堂々とDoji Isakaの名で参加ギャラの小切手が切られました(本名が記されたパスポートでは換金できませんでしたが・・・)。
「思えば、ドジという名前にはとても良い意味が含まれています。10回トライして9回失敗しても、最後の1回で成功すればいいという、ドジを踏むことを恐れないチャレンジスピリッツにつながるからです」
新しい名前で呼ばれるようになってからというもの、失敗を恐れずなんでもチャレンジする気持ちが沸いてきたというドジさん。1976年の第1回全日本プロサーフィン選手権でも優勝を果たしましたが、その後はウインドサーフィンやヨットなど、別のマリンスポーツの世界にもどんどん足を踏み入れていきました。

「プロの初代チャンピオンになったからといって、賞金だけで生活していけるほどサーフィンは甘い世界ではありません。当時、私はサーフボードの製作で生計を立てていましたが、後世に評価されるような美しいボードづくりをめざし、それを継承してくれる人材を育てようと考えていました。
ところが、いくら良いボードをつくっても、なかなかその評価が上がるというものではありませんでした。若者文化であるサーフィンに対する価値観が、そこまで育っていなかったのです」
なぜ自分はサーフィンをするのか? その原点に戻って考えてみると、大会で勝つことが目標ではありませんでした。烏帽子岩で海賊ゴッコをしたように、仲間を集めて海で楽しく遊びたいという思いが心の底に脈々と流れていたのです。
それなら、選手にこだわる必要はありません。ドジさんは、一般の人でも理解できるやさしいトークでサーフィン大会のDJを務めて人気を博す一方、風がなければ観戦者も交えて浜でさまざまなゲームを楽しむウインドサーフィンの大会を企画。その手腕が買われて、スノーボードの普及にも力を貸すようになっていきました。 (※続きます)