

 |
|||
 |
|||


1953年、千葉県津田沼生まれ、東京育ち。大学時代はヨット部に所属し、神奈川県三浦市の諸磯湾をベースにクルージングやレースにいそしむ。卒業後はヨット・モーターボート専門出版社(株)舵社に勤務し、編集長を経て現在は常務取締役編集局長。
おもな役歴:マリンジャーナリスト会議座長、植村直己冒険大賞推薦委員会委員、国土交通省「プレジャーボート利用改善に向けた総合施策に関する懇談会」、「プレジャーボート利用情報システム構築委員会」、「小型船舶操縦士制度等検討小委員会」、「沿岸域における適正な水域活用等促進プログラム」等の委員、全国首長会議交流イベント「ぐるっと日本一周・海交流」実行委員会顧問、B&G財団評議員。
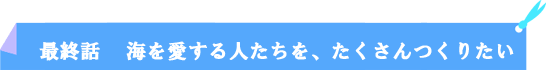

昨年、大都市を流れる運河や河川、不要となった倉庫群や荷揚げ岸壁跡地等の有効利用について検討する、国土交通省の「沿岸域における適正な水域活用等促進プログラム」の本省委員会ならびに地方委員会の委員を兼務した田久保さん。問題提起のひとつとして出されたのが、東京の運河の一角に『誰もが自由に使える桟橋設置の可能性について』でした。そうした桟橋を、ヨットやボート、カヌーに乗る人たちに利用してもらおうという案が浮上しましたが、「桟橋にゴミを捨てられたらどうする」、「桟橋で事故が起きたらどうする」、「不要になったボートを桟橋に繋いで捨てる人が出てくるかもしれない」といった細かい問題が次々に出てきて、議論が空転してしまいました。
「自由に利用できる桟橋の可能性を議論するなんて、海や河川に対する行政の姿勢もずいぶん変わったものだと感心しましたが、自由の奥には自己責任の原則が控えています。プレジャーボート先進国と呼ばれている欧米やオセアニア諸国の海岸には、ゴミがほとんど落ちていませんし、公園のようにきれいに整備された運河でプレジャーボートが自由に行き来している光景もよく見ます。

なぜ、こうした国々の水辺ではモラルやマナーの問題が起きないのかといえば、彼らには何世紀にもわたって海や運河を身近に感じ、親しんできた歴史があって、水辺の利用について自己責任が確立されているからなのだと思います」
身近に触れるものについては、大切に扱おうという意識が芽生えます。ところが、わが国ではいつしか「海は危険だからプールで泳ごう」、「川で遊ぶと危ないからフェンスを張って人を遠ざけよう」といった考え方が一人歩きするようになってしまいました。水辺が身近な存在ではなくなってしまったのです。
「戦後の復興を急ぐため、港や運河が産業優先になったことは仕方のないことだと思います。また、教育面では、水辺から子どもを遠ざければ安心だという風潮が高まりました。しかし、そのためにいわゆるフェンス行政が進んでしまい、多くの人々が公共の水辺に対する自己責任の感覚を見失っていったような気がします。海や川が身近なものでなければ、ゴミを落としても平気でいられるし、桟橋を壊したところで、『どうせ役所が直すだろう』と開き直ることもできるようになるのです」
夏になると、毎日のように水難事故のニュースが流れますが、その多くはちょっとした注意で防ぐことができるケースだと、田久保さんは指摘します。

「早い話、海や川に潜む怖さを知らない人が多いのです。離岸流(リップカレント)にしても、B&G海洋体験セミナーやB&G体験クルーズに参加した子どもたち、そして日頃、地域海洋クラブで活動している子どもたちならレクチャーを受けて知っていますが、一般の多くの子どもたちや、その親たちさえも知らないようです。
以前、オーストラリアへ取材に出かけたとき、あるヨットクラブでは子どもと母親を同席させた海の安全教室を開いていました。子どもたちだけに教えるのではなく、家族を含めて海の理解を深めてもらう努力が大切だと思いました。
また、このクラブの活動ではグループごとに小学校の上級生が下級生の世話を行い、全体的には大学生のボランティアが子どもたちの活動を支えていました。子ども同士で、グループの行動にある程度の責任を持たせると、どれだけ他人の世話をするのが大変なのかが理解できるようになります」
海洋体験セミナーや体験クルーズでも、異年齢の子どもたち同士で班を組み、上級生が下級生の面倒をみる仕組みにしています。子ども同士で、自分たちの行動にある程度の責任を持つという体験は、人生の大きな糧になるはずだと田久保さんは言います。
「体験クルーズのフェアウェルパーティーで子どもたちが流す涙の奥には、仲間と励ましあいながら船酔いなどの辛い経験を乗り越えた達成感もあるはずです。海の上に逃げ場はありませんから、辛くても陸地に着くまでは耐えなければなりません。それを子どもたちは身をもって知るわけですから、仲間同士お互いに励ましあえるのです」
人間教育の場として海は最適なフィールドですが、どのような方法で子どもたちを海に送り出してあげるか、よく考えてみる必要もあると田久保さんは指摘します。
「アメリカのあるパラグライダー教室では、初心者はいきなりインストラクターとタンデム(2人乗り)で空を舞うそうです。その楽しさを存分に知った生徒は、その後、どんなに辛い練習があっても必死に挑んでいくそうです。これはノンストレス教育と呼ばれているもので、最初に恐怖感などのストレスを与えずに楽しい経験をさせるのです。その楽しさを体験してしまうと、そのために必要な技術や知識の習得が格段に早い、という教育方法です。
近年、わが国の大学ヨット部はどこも部員が減って廃部の危機にあるところも少なくありません。なぜ、そうなったのかといえば、このパラグライダー教室の逆を行っているからなのだと思います。1年生は奴隷で4年生は王様だとよく言われますが、せっかくヨット部に入ったのに上級生になるまでヨットを操船させてもらえないのでは、最初から入部を諦めてしまう学生も多いはずです。
また、いま全国に大学ヨット部のOB、OGが10万人以上いるといわれていますが、社会人になってからもヨットを続けている人はごくわずかです。競技ばかりをして4年生を卒業すると、燃え尽きてしまって、ヨットはもううんざり、という状況に陥るケースもあります。ヨット本来の楽しさと出会えないまま卒業してしまうのですね」

「なぜヨットに乗りたいのか、なぜ海に出たいのか、原点に戻ってマリンスポーツを考えてみる必要がある」と、田久保さんは問題を投げかけます。一般のヨットクラブなどでも、最初から「これをしたら危ない」、「あれをしたらイケナイ」などと注意事項ばかりを詰め込んでいるところもあります。最初から厳しいことばかり教えていると、怖くなって不必要に身構えてしまう初心者も出てきてしまいます。
ノンストレス教育が行き届いたパラグライダー教室では、ベテランのインストラクターが操縦しながら、あらかじめ安全を確認した、ごく簡単なルートを飛ぶだけなのだそうですが、初心者にしたらそれだけでも感激です。ノンストレス教育では、熟練者によって作成される最適なカリキュラムが求められます。マリンスポーツにしても、普及の鍵はインストラクターの質、つまり『海のことをよく知った、良き兄貴(姉貴)たちの資質』にかかっていると、田久保さんは語っていました。(※完 )