|

 「病気を治す医者」から「病気をつくらない医者」をめざして疾病予防運動施設「ウェルビーイング・ポチ」を建設した、石井 馨先生。 実家の内科医院と掛け持ちで忙しい日々を送っています
「病気を治す医者」から「病気をつくらない医者」をめざして疾病予防運動施設「ウェルビーイング・ポチ」を建設した、石井 馨先生。 実家の内科医院と掛け持ちで忙しい日々を送っています |
小学生から中学生にかけてスポーツの才能を大いに開花させた石井先生。ご自身は器械体操に力を入れていましたが、陸上競技大会や水泳大会などにもよく借り出され、高校進学時にはスポーツ推薦の話もありました。
「子どもの頃はスポーツばかりに熱中していましたから、いま私が医者になっていると聞いたら、きっと小中学校時代の同級生は驚くと思います。しかし実家が内科の開業医で、私は長女で跡継ぎの立場でしたから、高校に入る時点で医者の道を選びました」
医師になると決めて、一時的にスポーツから身を引いた石井先生。それでも、医学の道に進むのならスポーツマンが多い職場がいいと、外科医の道を選びました。
「当時の外科といえばスポーツ好きでバンカラ気質の先生がたくさんいましたから、私の性に合っていると思ったのです。また、外科医の心得があれば、路上で急に倒れた人がいても人工呼吸などをしながら助けられますから、そんなイザというときの人助けに憧れを感じたのです」
もっとも、石井先生の実家は内科の医院。ご自身が志した外科医の仕事を8年ほど経験した後、将来のことを考慮して内科の勤務医として再スタートを切ることになりました。
「そもそも家のことを考えて医者になったわけですから、好きで選んだ外科の仕事ばかりをしてはいられなかったのです」
家の事情もあって内科医に転身した石井先生。外科医として経験を積んでから、再び内科の勉強をすることだけでもたいへんな労力が必要ですが、加えて、外科と内科それぞれを頼ってやってくる患者さんの事情の違いにも戸惑いを感じていきました。
|
静岡県浜松市にある疾病予防運動施設、医療法人社団しずや会「ウェルビーイング・ポチ」(TEL:053-434-5909)。20mプールやトレーニングジム、フロア運動スタジオなどを備えています |
「大雑把な言い方ですが、外科は悪くなったところを手術して切り取ってあげる仕事です。つまり、最初から患者さんに対して自分ができることが、かなりはっきりしているのです。当然、その結果も具体的に出てきますから、手術が成功したら『先生、ありがとうございました』と患者さんからお礼を言われることも多く、自分の力が患者さんのお役に立ったことが実感できます。
ところが、内科で診察する病気のなかには生活習慣病のように食事や生活の仕方などに問題がある場合が多く、症状を改善する薬は処方できても根本の原因を医者の手で切り取ってあげることが、なかなかできません。生活習慣病の原因を取り払う一番の方法は生活の改善ですが、わずかな診察時間で日々の生活習慣を正すにはとても難しい面があります。
実際、生活習慣病の患者さんを診るときは、『食事に気をつけてください』、『お酒は控えてください』といったやり取りになりますが、そのような説教めいた話に感謝する患者さんは、そう多くありません」
生活習慣病のように患者さん本人が病の原因をつくっているケースでは、医師の努力にも限りがあり、患者さんの協力がなければ病状は良くなっていきません。「説教はいいから、早く薬を出してくれ」などと、心配する医師の気持ちを忘れて自分に原因がないように振舞う患者さんもいるわけです。
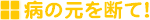
内科医になった石井先生のもとを訪れる患者さんの大半は、生活習慣病を患っていました。「お酒は控えてください」、「バランスの取れた食事を心掛けてください」と、生活の改善を呼びかけるなかで、石井先生は悩みを深めていきました。
 手前右は会員の食事相談などにも応じる栄養士の妹さん。指導を担当するスタッフ(後列の4名)は勉強熱心でとても頼れる存在だそうです
手前右は会員の食事相談などにも応じる栄養士の妹さん。指導を担当するスタッフ(後列の4名)は勉強熱心でとても頼れる存在だそうです |
「数分程度の診察時間で生活改善の指導などは十分にできませんし、患者さんが診察の場で医者の話にうなずいても、家に帰ってからは患者さんご自身が自覚しなければ意味がありません。外来で生活習慣病の患者さんたちをたくさん診ているうちに、『これは医者が直す病気ではなく、患者さんが生活習慣を正しながら直していく病気なのだ』という思いが日増しに高まっていきました。
しかも、糖尿病が進行すると、やがて心筋梗塞や脳梗塞で苦しむ患者さんが出てきます。そこで、また新たな治療が必要になるという悪循環があるわけで、そのようなジレンマにも悩むようになっていきました」
糖尿病が元で心筋梗塞などを患った人たちを前に、「もし、こうなる前に生活習慣を正す指導をしっかり行っていれば」と、医師としての自分を責めてしまうときもあったという石井先生。そんな矢先、衝撃的な出来事が起きました。
「以前から診察していた糖尿病のある患者さんが、たまたま私が当直していた夜に救急車で運ばれてきました。糖尿病が元で動脈硬化を起こし、心筋梗塞で倒れてしまったのです。担架で運ばれる最中、その人は私の手を握りながら『先生、大丈夫だよね。助かるよね』と口にしていましたが、生きているにも関わらず、すでに手は冷たく、私たち病院のスタッフには、もう手遅れな状態であることが分かっていました。このとき握られた冷たい手の感触は、いまでも忘れることができません。そして、この出来事を思い出すたび、『もう、こんなケースは二度とつくりたくない!』と思うのです」
|
取材当日も、会員の皆さんが元気でプールに入っていました |
この患者さんの場合も、生活習慣を正す指導がしっかり行われていたら、もっと違った人生になったはずだと語る石井先生。糖尿病のように痛みを伴わない病気は、しつこいぐらいに指導する必要があり、それを実践するためには数分間の診察だけでは無理があります。
そんな悩みを抱えながら、勤務医を辞めて実家の医院を手伝うようになった平成4年のある日、興味を引く話題が飛び込みました。プールなどの運動施設を病院内に設けてもよいという、医療法の改正でした。
実は石井先生、内科医になって悩む日々を送るなかで、健康指導に少しでも役立てようとスポーツ医学や栄養学を学ぶ一方、過食症などがメンタル的な理由から起きるケースもあるため、心理相談員の資格さえも取得。自分なりに生活習慣の指導法を研究し続けていました。ですから、このような法改正は願ってもない追い風でした。
「この法改正は内容的には規制緩和ですが、プールをつくるための公的助成はありませんし、施設の利用に関しても医療には直接関係ないとされて健康保険も使えません。しかし、このような施設が病院内にあれば、診察とは別に生活習慣病の指導をしっかり行うことができます」
石井先生は、ただちに家族と話し合い、従来の医院の隣にプールを備えた運動施設の建設を決心しました。
 施設3階に設けられた20m3コースのプール。一見、普通のプールに見えますが、疾病予防運動施設としてのさまざまなノウハウが投入されています
施設3階に設けられた20m3コースのプール。一見、普通のプールに見えますが、疾病予防運動施設としてのさまざまなノウハウが投入されています |
「施設を建てるには相当な資金が必要で、建てた後も経営的なリスクが伴いますから、まさに清水の舞台から飛び降りるような覚悟で家族を説得しました」
申請を出して認可が下りるまで2年ほどの月日がかかりましたが、その間、石井先生は民間のスポーツジムなどを見学して運営システムや経営ノウハウを勉強。その結果、プールを備えた3階建ての施設は「ウェルビーイング・ポチ」という会員制の疾病予防運動施設としてスタートすることになりました。
ちなみに、「ウェルビーイング」とはWHO(世界保健機関)憲章に記された「健康であり続ける」という意味の文言で、「ポチ」という言葉には、誰もが犬と散歩できる健康な体でいてほしいという願いが込められています。 (※続きます) |



