|
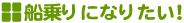

子どもたちにヨットを教える小松さん (プールでOPヨット体験:愛媛県今治市) |
戦後の復興が進む昭和20〜30年代にかけて、横浜の港町で育った小松さん。活気あふれる波止場や波が打ち寄せる磯などが遊び場だったそうです。
「家から自転車を10分も走らせると横浜の大桟橋にたどり着きました。たくさんの船が行き来する景色を見ながら遊んでいましたから、自ずと船に興味を抱いていきました。また、よく釣りに出かけた場所が当時の横浜ヨットハーバー(現:岡本造船所)でした。そこには、関東周辺の大学ヨット部がこぞって艇を置いていましたから、釣り糸を垂れながら彼らの練習をよく眺めていたものです」
船やヨットを自然に目にすることができる環境で育った小松さん。夏休みの宿題では、木を削ってヨットの模型を作ったこともありました。
「ヨットの模型は思いつきで作っただけのものでしたが、横浜という場所柄もあって、私も遊び仲間も、みんな海や船になんらかの思いを馳せていました。当時、私たちの間では、プロ野球の選手や飛行機のパイロットに負けないくらい船長の仕事が憧れの職業になっていたものです」
小松さんの場合、そのような海や船への憧れは叔父さんの存在によって拍車がかけられました。
「たまたま、叔父が船乗りだったんです。私が子どもの頃といえば海運業が華やかな時代でしたから、子どもの目からも叔父がとても輝いて見えました。昔の映画に出てくる、粋なマドロスの雰囲気があったのです」
船を下りるたびに、叔父さんは小松さんを連れて繁華街に繰り出し、さすがにお酒は飲ませてもらえませんでしたが、おいしい食事をたくさんご馳走してくれたそうです。
「あの頃の船乗りは羽振りが良くて、陸に上がると豪快にお金を使っていました。当時の私には『港、港に女をつくって・・・』というマドロスの歌い文句の本当の意味は知りませんでしたが、子どもながらに叔父の姿を見ながら、行く先々に待っている人がいるほど皆に慕われるカッコイイ存在なんだな、と憧れの念を抱いていました」
叔父さんのような、粋な船乗りになりたい。そんな思いは、ある出来事を機会にヨットの世界へ向けられていくことになりました。

 ライフジャケットの大切さを子どもたちに話す小松さん(プールでOPヨット体験:茨城県行方市)
ライフジャケットの大切さを子どもたちに話す小松さん(プールでOPヨット体験:茨城県行方市) |
小松さんがマドロスの叔父さんを慕っている傍ら、小松さんのお父さんは運送業を立ち上げて仕事に追われる日々を送っていました。豪快に生きる叔父さんと、毎日、忙しく働くお父さん。そこにギャップを感じてしまった小松さんは、しだいにお父さんを敬遠するようになっていきました。
「誰でも一度はあると思うのですが、私も中学生になると反抗期を迎えていました。叔父に憧れ、船乗りになる夢を漠然と抱きつつ、家のなかでは親に口ごたえしながら、うつうつとした日々を過ごしていたのです」
私立の中学へ進学した小松さん。それまでは近所の仲間と仲良く遊び、クラスのなかでも活発に行動していましたが、いろいろな地域から知らない生徒がたくさん集まる私立の中学に入ると、顔なじみがいないためか人前に出ることが苦手になってしまいました。しかも、そんな状況は高校に進学してからも続きました。
家でも学校でも、うつむいた生活を送る小松さん。ところが、ある日、思わぬことが小松さんの生き方を変えました。
「高校1年生のときでした。テレビで高校野球を見ていたら、甲子園でプレーする選手たちがとても輝いて見えたのです。自分と同じ高校生なのに、彼らは1つの大きな目標に向かって、とても一途な生き方をしているわけです。ふてくされて、ヤル気のない毎日を送っている自分と比べ、その大きな差を痛感しました」
自分も目標を持って生きよう。そう心に誓った小松さん。そのとき、まっさきに頭に浮かんだのは大海原を走る船の姿でした。
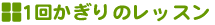
 B&GOP大会大分・福岡の両大会でレース委員長を務め、ヤングセーラーを激励!
B&GOP大会大分・福岡の両大会でレース委員長を務め、ヤングセーラーを激励! |
その後、新学期を迎えてクラス変えがあったとき、親しくなった友人の兄が早稲田大学のヨット部にいることを知りました。
「思わず、これだと思いました。ヨットを覚えれば、高校生でも自分の力で海に出ることができますから、とことん打ち込んでみようと考えたのです。
さっそく友人の兄さんを訪ね、ヨットに乗せてほしいとせがんだ小松さん。しかし、期待した返事をもらうことはできませんでした」
「後に、私は早稲田大学ヨット部のコーチを10年間受け持つことになりましたが、大学の資材であるヨットを勝手に持ち出し、部員でもない他人を乗せて遊ぶことなど許されるわけもありません。その兄さんは、『まずは自分でヨットを手に入れろ』とアドバイスしてくれました」
「ヨットって、いくらするんですか?」と小松さん。兄さんの返事は、中古のディンギーなら15〜20万円ほどで手に入るとのことでした。
「当時、学卒の初任給が4万5千円ほどでしたから、夢のような金額でしたが、私はなんとかしてディンギーを手に入れてみせると心に決めました」
それからというもの、小松さんの頭のなかはヨット一色に染まりました。ディンギーを買ったら乗せてあげるという約束で、昼食は友人たちの弁当を分けてもらい、昼食代に家からもらう100円をコツコツと貯金。そして夏休みになると、毎日、港に出向いて沖仲士という日雇い労働で汗を流しました。
「沖仲士とは、沖に停泊している貨物船の荷物を、荷受用の小さな船に移し変える仕事です。毎朝、波止場に行くと手配師が人足を集めているので、年齢を偽って働きました。仕事はとても過酷で、高校生の私などは1日働くと、翌日は体がまったく動きません。ですから1日おきに働きましたが、給金は1日5千円と魅力的でした。新人サラリーマンの月給を10日ほどで稼いでしまうのですから、当時としたら、たいへんな額です」
夢をつかもうと必死で働いた小松さん。その甲斐あって、秋には12フィートのディンギーを手にし、江の島ヨットハーバーに置くことができました。
「喜び勇んで、友人の兄さんに教えを請いましたが、いつも陸上でセールの上げ方やタックのシミュレーションなどを行うばかりで、なかなか海には出してもらえません。後で分かりましたが、大学に入って初めてヨットに接した学生などが、とても人にセーリングのノウハウなんて教えられる訳もないのです」
業を煮やした小松さんが、どうしても海に出たいと談判すると、友人の兄さんはヨット部のなかでも腕利きの部員を紹介してくれました。ただし、レッスンは1日だけ。それでも、小松さんは飛びつきました。
「海に出て人からヨットを教わったのは、後にも先にもこのときの1回だけでした。しかも、レッスン当日は風が強く、とても初心者が海に出られるようなコンディションではありませんでした」
本来なら出港をあきらめるところでしたが、小松さんが海に出ることを強くせがんだため、ハーバーを出て15分ほどは走ることができました。短い時間のなかで、出港から帰港までの一連の動作を必死になって頭に叩き込んだ小松さん。その後は、この1回だけの体験を頼りに、果敢にも1人で海に出ていくようになりました。
実は小松さん、貯金を始めた段階で「ヨット百科」という本を読み始め、ディンギーを手にしたときには、すべてのページを暗記するほど徹底的に読破していました。たった1回、しかも15分のレッスンだけを頼りに1人で海に出て行くようになった陰には、なんとしてもヨットを覚えたいという信念のもとで、こうした地道な努力があったのです。
余談になりますが、小松さんを海に出してくれた腕利きの部員は、「大谷たかを」という人でした。大谷さんは、その後、レーザー級ディンギーの普及に携わる傍ら、国際審判員として世界中のヨット競技で活躍。日本でも指折りのヨット指導者として国内外で知られるようになりました(現:日本セーリング連盟理事)。日本を代表する2人のセーラーが、それぞれ無名の時代に顔を合わせたことには、なにかの縁を感じてしまいます。
続く
|




