|
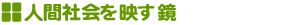
 |
|
国土交通省が進めている
「海辺の達人養成講座」活動風景
|
国土交通省港湾局が着手した「海辺の自然学校研究会」の専門委員に選ばれるなど、年々、広がりをみせる海野さんの仕事。海野さん自身も、まだまだ力を入れたいことがたくさんあると語ります。なかでも環境問題に関しては、第1話で紹介したように大学を選んだときの動機でもあったため、格別な思いを抱き続けています。
「発見されたものだけで350万種類もの生き物が暮らしている地球にあって、人間というたった1種類の生き物が地球全体の酸素の6割を消費していると言われています。ですから、その意識を持って人間が何らかの行動を取らないかぎり、オゾン層の破壊や地球温暖化といった環境の悪化は食い止めることができません。生物資源の再生産量(リサイクルできる量)は、すでに1980年代でマイナスへ転じてしまっており、このままのペースで資源の消費が続けば地球の環境は想像もできないほど劣悪な状態になってしまうのです」
こうした問題については、自然に親しんだことのない人ほど鈍感な傾向にあると海野さんは指摘します。自然体験教育は、私たちが暮らす地球を真剣に考えるうえで、とても重要なキーワードになっているのです。あまり自然に関心のなかった三宅島の子どもたちも、海辺の体験授業を通じて島のサンゴや魚、鳥などを自分たちの宝物だと思うようになりました。
 |
|
〜磯の観察〜
葉山マリンキッズの活動風景
|
「私の経験上、おおむね40歳代後半以上の人たちは自然の大切さを多少なりとも感じているようです。この世代は、子どもの頃に野山や海辺を遊び場にしていたことが多かったからだと思います。しかし、それ以下の年齢になると、自然体験が乏しいためか、なかなか環境問題を受け止められない人が目だってきます。今、一般社会でも学校のなかでも、とても凶悪な事件が起きて問題になっています。こうした事件の1つ1つの根をたどると、いろいろな共通点が出てくると思いますが、その1つとして自然体験の乏しさがクローズアップされてくるような気がしてなりません。自然のフィールドで遊ぶことは、いっしょに行動する仲間への思いやり、そして自分たちを包み込んで遊ばせてくれる自然に対する思いやりが育まれます。この経験が乏しければ乏しいほど、他人や社会が見えてこなくなる恐れがあるのです」
海と子どもには、似たところがあると海野さんは言います。海は、ゴミ問題を含めて生産物が終末する大きな場であり、子どもは大人社会の生活の歪を受けやすい。つまり、海も子どもも人間社会の末部を映す鏡になっているというわけです。ですから、海を大切にする人が増えれば増えるほど社会も良くなるし、子どもが育つ環境も良くなっていくのではないかと、海野さんは考えています。
「今、海の環境教育を体験している子どもたちが大人になって自分たちの子どもができたとき、海で学んだことを活かして良い社会をつくることができたと、みんなで思えるようになっていたら、すばらしいですね」
現在の子どもたちを海にいざなうことは、将来の社会をより良いものにするための第一歩になる。海野さんは、そう信じながら活動しています。

 |
|
〜スノーケリング(下田キャンプ)〜
葉山マリンキッズ活動風景
|
自然体験が乏しい子どもや大人に、どうしたら自然の大切さをしっかり伝えることができるでしょうか。最初から海に入るのをいやがったり、怖がったりする人もいるはずです。
「確かに、今、私が活動している葉山の子どもたちと都会からやってくる子どもたちの間には、海に対する意識に大きな差を感じる場合が少なくありません。ひと口で言えば、普段からオーシャンファミリーの活動に参加している葉山の子は放っておいても海に入って遊び始めますが、体験授業などで私たちのところを訪れた都会の子は浜に座り込んでしまいます。運動能力にも歴然とした差があり、都会の子どもたちは信じられないような場面でよく転びます。そして、海のにおいや海水の塩辛さ、波や海風を嫌い、1つのことを続ける忍耐力にも欠しく、ちょっと寒さを感じただけで助けを求めます。しかし、だからと言って悲観はしません。なぜなら、どんな子どもでも胸に秘めた海への思いはあるからです。これはある種、本能的なものかもしれません」
ヤドカリなどの海の生き物を見て、最初は「気味が悪い」と二の足を踏んでいた子どもでも、慣れてくると夢中になって触れ始めるそうで、そんな姿を見て、引率の教師や保護者なども、「こんなに子どもたちが夢中になった授業は初めてだ」と感激することが少なくないそうです。こうした子どもの行動は、長い歴史のなかで人間と自然とが深く関わりあってきた証拠であり、その本能的な結びつきが、文明の発達とともに海や山から遠のいて生活することが多くなった現代人の脳裏にもまだはっきりと刻印されているのです。
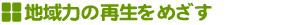
 |
|
〜スノーケリング〜
葉山マリンキッズでの指導風景
|
海の環境教育を通じて多くの子どもたちと接してきた経験から、海野さんは地域が担う教育の重要性についても着目するようになりました。
「教育には、学校教育、家庭教育、そして地域の教育があると思うのですが、昔と比べて地域の教育力が格段に低下していることを感じます。地域の教育と聞いてピンとこない人もいるでしょうが、これは要するに人を育てる役目を地域も担っているということです。人間は、大人になるまで多くの人に育ててもらう必要があるわけですが、その役を担うのは親であり、学校の先生であり、そして子どもが暮らす地域の人たちなのです。昔は、祖父母をはじめ近所のおじさん、おばさんからも子どもたちはいろいろなことを教えられていましたが、今は核家族化の影響もあって、そういう人たちと子どもたちとが疎遠な関係になってしまいました。ですから、そんな地域との関わり合いに親が戸惑い、そんな親の子どもたちが戸惑いながら成長しているわけです。もちろん、高齢化社会、少子化社会と言われるようになって社会の構造自体が違ってきているのですから、昔の仕組みに戻せといっても無理はありますが、新しい社会構造のなかでどのような地域を創造していくかを真剣に考える必要があるのではないでしょうか。たとえば、老人ホームにしても人里離れた施設ではなく、グループステイで地域社会のなかで暮らしながら、ときどき地元の子どもたちが遊びに訪れるといった施策のほうが健全な姿に思えます。地域社会をどのように築き、そして地域の子どもたちをどのように育てていくべきか、行政のみならず地元の商店や企業なども参画しながら皆で考える必要があると思います」
 |
|
〜松の年齢について話をする海野さん〜
葉山マリンキッズでの指導風景
|
現在、海野さんはオーシャンファミリーの活動のなかで地元の子どもたちを対象にした「葉山マリンッキッズ」という組織を立ち上げていますが、その目的の1つは、子どもたちの育成を地域が考える仕組みづくりにあるそうです。3年前の初年度、「葉山マリンッキッズ」に参加した子どもは約20名。その輪が年々倍増して、現在は100名近い参加者で賑わっています。
「参加者が拡大したのは、子どもたちの親が口コミで活動の評判をしてくれたおかげです。井戸端会議で『葉山マリンキッズ』が話題にされ、忘れていた地域教育の大切さに気づいてくれた結果と言えるでしょう」
少年時代、生物学者になる夢を抱き、環境問題に刺激されて自然保護を伝える教師になり、自ら三宅島に渡って自然とともに暮らしながらその道を進み続けた海野さん。亡きモイヤー博士の遺志を継ぎながら、現在、国の公的な仕事を含めてさまざまな活動を展開していますが、まだまだ活躍の場は増えていきそうです。

感想をお送っていただいた方に、『KAZI』最新号を抽選で毎月10名様にプレゼントいたします。 郵便番号・住所・氏名・電話番号・感想をご記入の上、下記宛先にお送りください。
郵便番号・住所・氏名・電話番号・感想をご記入の上、下記宛先にお送りください。
●お葉書の方
〒105-8480 東京都港区虎ノ門1-15-16
B&G財団 プレゼント係
●メールの方
 koho@bgf.or.jp
koho@bgf.or.jp
当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせて頂きます。
|
|




