|
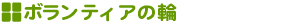
 |
| アクセスディンギーを操船する子ども達 |
JSAF(日本セーリング連盟)の仕事を一区切りさせた松本さんは、さっそく海の現場に戻ってセーラビリティという活動に力を入れるようになりました。
セーラビリティとは、障害を持った人にもセーリングの楽しさを知ってもらおうと、英国のRYA(王室ヨット協会)が1980年代から着手した活動で、日本でも現在、ジョイスティック型のティラーを使って手軽に操船できるアクセスディンギーを使いながら各地で組織が立ち上げられています。B&G財団でもアクセスディンギーの普及に力を入れており、江の島で活動を始めた松本さんたちの集まり(セーラビリティ江の島)にも2隻を無償で貸し出しています。
「バリアフリーで誰もがヨットに乗れる環境を作ろうと、江の島ヨットクラブをベースに活動を始めましたが、障害者や子どもたちを乗せるためにはサポートするスタッフが必要です。そのため、ボランティアでスタッフを引き受けてくれる人を募集したところ、中高年層を中心に大勢の男女が手を挙げてくれました」
応募の条件は、ヨットや海に興味があるかどうかという一点のみで、ヨットの操船歴はおろか年齢や性別などは問いませんでした。言うなれば、ボランティアスタッフにもバリアフリーに近い状態で集まってもらったのです。
「なんらかの仕事がお手伝いできれば、それでいいのです。ヨットの操船なんて知らなければ覚えてもらえばいい、そんな気持ちで募集を掛けました。実際、彼らの多くは、ボランティアはするけど自分たちもヨットを上手になりたいと、夢を膨らましています。セーラビリティを通じて、障害者も健常者も、それまでヨットに縁のなかった大勢の人たちが海に憧れを抱いてヨットに乗ってくれるようになったわけです。実に楽しく、実にすばらしいことだと思っています」
昨年に立ち上げたセーラビリティの輪は大きく広がり、今年はさらに40名のボランティアスタッフを集めることになりました。

このような新たな人の輪が江の島ヨットクラブ内に誕生した背景には、アクセスディンギーを通じて交流が生まれたB&G財団の存在が大きいと松本さんは言います。
「かつて、私が江の島ジュニアヨットクラブで試みた発想の多くは、すでに30年も前からB&G財団が目指していたものばかりです。親子ヨット教室しかり、合宿をしてディンギーで海を渡ることしかりです。このような親水活動を、全国のB&G海洋クラブが行っていると知ったときには、『なぜ、もっと早くB&G財団と一緒になって活動できなかったのだろうか』と、実に悔しい思いに駆られてしまいました。日本代表選手の強化やヨット組織の仕事ばかりに夢中になっていて、なかなか気がつかなかったのです」
 |
体験クルーズに参加した子ども達と
対談する松本さん |
今年に入って、松本さんはB&G体験クルーズにオブザーバーとして参加し、船上生活を子どもたちと一緒に体験。その後、江の島に海洋クラブを設立する旨をB&G財団に申請しました。クラブ活動を支えるのは、セーラビリティのボランティアスタッフとして集まった人たちが中心になるそうです。
「今、私が抱いている海洋クラブのイメージは、子ども中心の組織を指導者が見ていく従来のジュニアクラブのスタイルではなく、子どもたちが、よそのおじいさんやおばあさん、おじさんやおばさんたちと一緒に海で遊び一緒に学ぶ、大きなファミリーのような集まりです。一人っ子や核家族の子どもたちも一緒になって、彼らの親たちにも参加してもらい、家族的な雰囲気の中で大勢の子どもたちを鍛え育てていければいいなと思っています」
ボランティアスタッフの中からは、いろいろなヨットに乗りたいという声が高まったため、とうとう松本さんは有志を募って海洋クラブの活動用に大型のセーリングクルーザーも手に入れました。B&G江の島海洋クラブは8月に誕生することが決まりましたが、すでにクラブのメンバーになる皆さんの気持ちはどんどん前へ進んでいます。
※同クラブの活動については、あらためて取材する予定です。

 |
| クルーズを楽しむ松本さん |
病弱な幼年時代を過ごした松本さんが、たくましく生きるようになったのはヨットとの出会いがあったからにほかありません。ヨットと共に過ごした半生について、松本さんはこう語ります。
「私は、高校時代にヨットと出会うことができ、本を借りながら夢中になって独学でヨットのことを学び、そして海に出ていきました。これも、ひとえに私がヨットをとことん好きになったからできたことだと思います。ヨットのことをたくさん知りたいと思ったら、操船技術はもちろんのこと、気象や力学、造船工学、そして繊維化学といった実にさまざまな分野の知識を追い求めるようになります。要するに、ヨットを通じて勉強の視野がどんどん広がっていくわけです。これはヨットに限ったことではなく、たとえば音楽が好きになったら、楽器を操る技術だけではなく、音楽の歴史や文化、言語などにも興味が広がるはずで、それが人生の貴重な勉強になっていくのです。だから、子どもたちには『好きになって夢中になれるものを探しなさい』とよく言います。もちろん、何が好きなのか分からない子もたくさんいますが、いろいろな経験を積めば、その中から自分が本当に夢中になれるものが1つは見つかるのではないでしょうか。そして、何か夢中になれるものに出会えたら、『自分には才能がない』などと思ってすぐ諦めず、努力を重ねてみることが大切です。なぜなら、生まれながらの天才なんていないからです。私にしても、ヨットに夢中になってからは、自分が幼い頃に病弱だったなんてことを気にする暇はありませんでした」
好きになったヨットのおかげで、実にたくさんの人との出会いがあり、ときにはその人たちの助けを借りることもできたと語る松本さん。好きなことをみつけて努力したからこそ、人の輪を広げることができたのだと思います。
 |
| タヒチでクルーズ |
「子どもたちには限りないチャンスがあります。だからこそ、いろいろなことにチャレンジしてもらいたいと思います。自分がドキドキするものに挑んでみる。それは、その人にとっての冒険です。冒険をしなくても人の一生は終わってしまいますが、新しいものを求めて冒険したその体験は、人生をきっと豊かなものにしてくれると思います」
今、松本さん自身もB&G江の島海洋クラブという新しいチャレンジに意欲を燃やしています。きっと、皆が胸をドキドキさせるような、楽しく有意義な活動が展開されていくことでしょう。
|




