|

 |
|
始めてのカヌー体験(小学6年生)
☆奥が稲谷君☆
|
平成13年の春先、当時、B&G東京海洋センターでカヌーピアザ江東の企画運営を担当していた坂倉課長のもとへ、「不登校で悩む中学生の長男をカヌーに乗せてみたいのですが、受け入れていただけるでしょうか」という内容の電話が入りました。話の主は稲谷君のお母さんでした。
「耕一は小学6年生の頃から不登校になって家にこもりがちだったので、なんとか家の外に連れ出して元気になってもらいたいという思いでいっぱいでした。親子でいろいろ話をしてみると、学校は無理でもカヌーなら乗ってみたいと言うのです。小学6年生のとき、どうしても学校に行けないので、夏休みを利用して農村生活を体験するツアーに1人でもよいから参加したいと言い出しました。その際、川でカヌーに少しだけ乗せてもらっていました。本人にとっては、愛読書であった椎名 誠の本の内容とだぶり、この経験がかなり新鮮に感じられ、以後、ますますカヌーや椎名 誠の本にひかれていったようです。おそらく、本を手にするたびに自分でも漕いでみたくなっていったのだと思います」
中学生になっても不登校が続く稲谷君を心配して、お母さんは新聞や区報、雑誌などを頼りにカヌー教室を探しましたが、どこも年齢制限を設けているため諦めざるを得ませんでした。それゆえ、B&G東京海洋センターに電話を入れたときも不安を隠せませんでしたが、電話の向こうから聞こえてきたのは、「今年のカヌーピアザ江東は毎週水曜日の午後に開催しますので、地元の小学生や仕事をリタイアされた中高年者の参加が多いと思いますが、それでもよろしければどうぞいらしてください。歓迎いたします」という、うれしい言葉でした。
さっそく第1回目の教室に稲谷君を連れ出したお母さん。確かに、参加者は中高年者のグループのほかは小学生ばかり。水曜日の午後1時から中学生が参加していたら不思議に思われてしまうような状況でしたが、稲谷君は戸惑う様子も見せず、ひたすらインストラクターの言葉に耳を傾けました。
 |
| 小学生にカヌーの乗り方を教える |
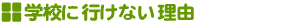
カヌーピアザでカヌーに乗ったときの第一印象を、稲谷君はこう振り返ります。農村の生活体験ツアーでカヌーに乗せてもらったことはありましたが、自分で漕ぐのは初めてでした。
「艇のバランスを取るのが難しく、パドルを手にするのも初めてだったので、最初はかなり苦労しましたが、なにより本で読むのと実際に乗るのでは楽しさが違います。漕ぐのは難しいなと思いながらも、水の上に浮かんでいることだけで実に気持ちがよかったです。しかも、日頃、運動していなかったため、体を動かして爽快な気分になりました」
普段は、近所の図書館に行って何冊か本を借り、それらを家で読みながら過ごすことが多かったという稲谷君。やがて、読んでみたい図書館の本もすべて読破してしまい、本当にただボーッと何もしないで過ごすようになった矢先のことでした。
「読みたい本がなくなり、だからといって家の外に出るのも億劫だという状況が続くなかで、このままではいけない、何かをしなければ自分は変わることができない、という気持ちは常にありました。心配する母に連れられて病院の精神科にも行きましたし、フリースクールなら通えるのではないかと見学に行ったこともありましたが、なかなか生活を変えることはできませんでした」
不登校という言葉の意味を、「ただ学校に行きたくないだけのこと」と解釈してしまう人も少なくないと思います。しかし、何もしないでボーッしていることで一番苦しんでいたのは、稲谷君自身でした。
「学校に行こうと思っても、家を出るときに胃が痛くなってしまったり、座り込んでしまうほど頭が痛くなったりしていました。朝、どうしてもお腹が痛くて、なかなかトイレから出られないことがよくありました」
学校への行き渋りは小学校入学当時からときどきあったそうですが、このように身体的な症状が出て長期的に学校を休むようになったのは6年生になってからでした。
「行き渋りは、新学期になったときや担任の先生が変わったときなどによく起きていましたが、体の具合が悪くなって動けなくなってしまうようなことは6年生になるまで見られませんでした。そのため最初のうちは、朝、トイレに入ったまま出てこないのは、学校に行きたくないから単にグズっているのだと思いました。親にも理解されないで、本人は相当辛かったことと思います」
はじめは、お母さんでさえ分からなかった稲谷君の苦痛。「学校に行きなさい」、「行きたくても行けない」という格闘が家の中で何カ月も続き、やっとのことでお母さんもお父さんも、真実に気づくことができたそうです。

 |
カヌーピアザ活動風景
☆江東区
横十間川☆ |
どうして学校に行こうとすると体の具合が悪くなってしまったのか、稲谷君本人ですら今でもその原因が分からないそうですが、カヌーピアザ江東に参加する際にはいっさい同様の症状が出なかったそうです。
第1回目の教室が終わったその日、稲谷君が親水公園の脇にある停留所でなかなか来ない帰りのバスを待っていると、後片付けをしていた坂倉課長から声を掛けられました。
「なかなかバスが来ないようだね。それなら、どうだろう? 後片付けを手伝ってもらえないかな?」
バスが取り持つ縁だったと、坂倉課長は振り返ります。久しぶりに体を動かして気分爽快だった稲谷君は、嫌な顔ひとつせず、B&G東京海洋センターのスタッフたちとカヌーを艇庫に運んで、ふたたび快い汗をかきました。
稲谷君の場合、不登校で悩んでいたとはいえ、2人の弟の面倒はよく見ていたし、家の手伝いもしていました。本人曰く、頼まれると断れない性格とのこと。このときも、手伝うことに何の違和感も覚えなかったそうです。
「今日はありがとう。本当に助かった。来週も来てくれるよね。一緒にカヌーに乗って、今日みたいに後片付けも手伝ってくれたら、うれしいな」
作業を終えて、ごく自然に坂倉課長の口から出た、お礼とお願いの言葉。このさりげないひと言が、その後の稲谷君の行動を変える大きなきっかけになっていくのでした。
|




