
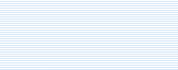
 |
|||
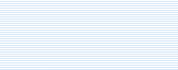 |
|||


1953年、千葉県津田沼生まれ、東京育ち。大学時代はヨット部に所属し、神奈川県三浦市の諸磯湾をベースにクルージングやレースにいそしむ。卒業後はヨット・モーターボート専門出版社(株)舵社に勤務し、編集長を経て現在は常務取締役編集局長。
おもな役歴:マリンジャーナリスト会議座長、植村直己冒険大賞推薦委員会委員、国土交通省「プレジャーボート利用改善に向けた総合施策に関する懇談会」、「プレジャーボート利用情報システム構築委員会」、「小型船舶操縦士制度等検討小委員会」、「沿岸域における適正な水域活用等促進プログラム」等の委員、全国首長会議交流イベント「ぐるっと日本一周・海交流」実行委員会顧問、B&G財団評議員。
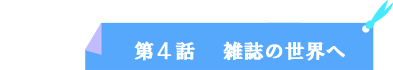

 企画・制作部のグラフィックデザイナーや取材記者、外注のコピーライターなどと、仕事の打ち上げを楽しむ田久保さん(右奥)
企画・制作部のグラフィックデザイナーや取材記者、外注のコピーライターなどと、仕事の打ち上げを楽しむ田久保さん(右奥) アウトドアー記事の取材現場で、スタッフとともにひと息つく田久保さん(中央)
アウトドアー記事の取材現場で、スタッフとともにひと息つく田久保さん(中央)
 ヨットそのものより、ヨットに関わる人物への興味を高めていった田久保さん。キャビンにおじゃまして、納得いくまでヨットのオーナーと話し込むことがよくあります
ヨットそのものより、ヨットに関わる人物への興味を高めていった田久保さん。キャビンにおじゃまして、納得いくまでヨットのオーナーと話し込むことがよくあります