

 |
|||
 |
|||


溝口 進 市長
昭和5年(1930年)生まれ。富山県立福野高等学校を卒業後、富山県庁入庁。その後、昭和57年から6期22年間にわたって旧福野町町長を務め、平成16年11月からは、同町を含む市町村合併で誕生した南砺市の初代市長に就任。
富山県南砺(なんと)市
平成16年、福野町など8つの町村が合併して誕生。人口58,605人(平成18年2月現在)。富山県の南西部、岐阜、石川両県の境と接する場所に位置し、広さは琵琶湖とほぼ同じ。山間部は美しい自然を有する白山国立公園に指定され、平野部には水田地帯が広がる。
 学生時代からスポーツが大好きだった、富山県南砺市の溝口 進市長さん。いまから25年前、旧福野町町長に初当選した際は、地域住民が気軽に利用できる体育施設が乏しいことを痛感し、地域海洋センターの誘致に尽力。
学生時代からスポーツが大好きだった、富山県南砺市の溝口 進市長さん。いまから25年前、旧福野町町長に初当選した際は、地域住民が気軽に利用できる体育施設が乏しいことを痛感し、地域海洋センターの誘致に尽力。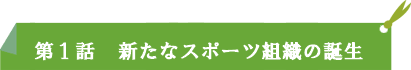
20歳代にはバスケットボールを、30歳代になってからはソフトボールと、常にスポーツを楽しんでいたこともあり、県庁職員時代から各地域に一般社会人向けの体育施設が少ないことを気にかけていた南砺市の溝口市長さん。1982年に旧福野町の町長に就任すると、ただちに町内の体育施設を調べました。

 海洋センターの竣工式には大勢の住民が参加。溝口町長さんは、建設の無事を祈ってたくさんの餅をまきました
海洋センターの竣工式には大勢の住民が参加。溝口町長さんは、建設の無事を祈ってたくさんの餅をまきました
社会人になってからもスポーツを続けていた自らの経験を基に、なんとかして町内に一般人向けの体育施設をつくりたいと願った溝口町長(当時)さん。そんな思いから、昭和60年(1985年)にB&G地域海洋センターの募集制度を知ると、迷わず次年度の応募を決めました。
「これこそ、子どもからお年よりまですべての地域住民が利用できるすばらしい施設であると思いました。ところが、東京のB&G財団へ何度も足を運んで陳情を繰り返したものの、この年の募集には受かりませんでした。『温水設備は町の予算でつくりますから、そのためのプール施設にしていただきたい』と、少々無理を言ってしまったからだと思います」
長年温めてきた一般向けの体育施設が実現できると意気込み、ちょっと大きな夢を抱いてしまった溝口町長さん。しかし、温水プールこそ叶わなかったものの、翌年(昭和62年度)の募集では晴れて誘致を決めることができました。
溝口町長さんは、海洋センターを誘致するにあたって自ら基本構想を頭に描きました。
「助成事業などで建設する公共施設は、とかく辺ぴな場所になりがちです。用地だけは自前で確保しなければならない場合が多く、そのため、手に入れやすい土地が選ばれる傾向にあるからです。しかし、海洋センターの場合は、より多くの住民に利用していただきたいという思いがあったため、町役場から数十メートルと離れていない誰にとっても便利の良い場所を買収しました。海洋センターは、“つくっていただくことが目的ではなく、それをいかに利用するかが目的でなければならない”と思ったのです」
 昭和63年、念願のB&G福野海洋センター (現:南砺市福野B&G海洋センター)は、盛大なオープニングセレモニーによって、その歴史の幕を開きました
昭和63年、念願のB&G福野海洋センター (現:南砺市福野B&G海洋センター)は、盛大なオープニングセレモニーによって、その歴史の幕を開きました念願の福野町B&G海洋センターは昭和63年に完成しましたが、竣工の段階で県から同町に派遣されていた山下 均さんという体育主事から、興味深い提案が出されていました。
「彼は文部省(当時)の海外調査に参加しており、その経験を基に『海洋センターという住民の誰もが利用できる施設を建設していただけるのであれば、町内を旧村単位の7地区に分け、それぞれに一般参加型のスポーツクラブをつくりましょう』というアイデアを考えたのです」
学校単位ではなく地域ごとにスポーツクラブがあれば、進学を境に活動環境が変わってしまうことはなく、子どもの頃から年配になるまで一貫して好きなスポーツに打ち込めます。こうした仕組みは主にヨーロッパ諸国で多く見られ、まさにB&G財団が設立当初に掲げた、ドイツの生涯スポーツクラブ構想“ゴールデンプラン”の発想でした。
 海洋センターの開設を祝してさまざまな競技の記念大会が開催され、その1つ1つに溝口町長さんは足を運びました。写真は、ゲートボール大会で始球式を行う溝口町長さんです
海洋センターの開設を祝してさまざまな競技の記念大会が開催され、その1つ1つに溝口町長さんは足を運びました。写真は、ゲートボール大会で始球式を行う溝口町長さんです山下さんのアイデアに溝口町長さんも大賛成。さっそく7つの地区に住民の誰もが参加できるスポーツクラブがつくられ、各クラブの活動は福野町スポーツクラブ連合というまとめ役の組織によって束ねられることになりました。
「どの自治体もそうですが、町には従来から体育協会が組織されていたため、『なぜ、スポーツクラブをつくらなければならないのか』といった異論もありました。しかし、バレーボールやバスケットボールなど、各種目に特化しながら選手を育てていく体育協会が縦の糸なら、誰もが参加して日頃からスポーツを楽しむスポーツクラブは横の糸の役割を持っており、この両方の糸が織り合って初めて実り豊かなスポーツ行政が実現できるのです」
山下さんが考えたスポーツクラブの構想は、溝口町長さんの強い後押しを受けて前進し、やがてスポーツクラブ連合が主催するあるイベントによって町民から熱い支持を受けるようになっていきました。(※続きます)