

 |
|||
 |
|||


1953年、千葉県津田沼生まれ、東京育ち。大学時代はヨット部に所属し、神奈川県三浦市の諸磯湾をベースにクルージングやレースにいそしむ。卒業後はヨット・モーターボート専門出版社(株)舵社に勤務し、編集長を経て現在は常務取締役編集局長。
おもな役歴:マリンジャーナリスト会議座長、植村直己冒険大賞推薦委員会委員、国土交通省「プレジャーボート利用改善に向けた総合施策に関する懇談会」、「プレジャーボート利用情報システム構築委員会」、「小型船舶操縦士制度等検討小委員会」、「沿岸域における適正な水域活用等促進プログラム」等の委員、全国首長会議交流イベント「ぐるっと日本一周・海交流」実行委員会顧問、B&G財団評議員。
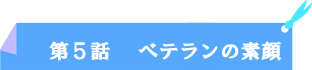

取材を通じて、ヨットやボートという乗り物もさることながら、そうしたフネに乗る「人間」そのものに対して大きな興味を抱いていった田久保さん。さまざまなシーマンと接しながら、彼らから大きな影響を受けました。
「ヨットやボートの取材では、艇の特長とか性能などを調べるより、オーナーやクルーと海の話をすることに喜びを感じていきました。舵社はヨット専門誌の出版社ですからメカニックな記事の要素も求められるのですが、私の場合はヨットに関わるさまざまな人たちの生き様に、大きな関心を持つようになっていったのです」
ヨットマンやボートマンはベテランになればなるほど繊細な神経の持ち主になると、田久保さんは言います。おそらく、海でいろいろな修羅場を潜り抜けながら五感が研ぎ澄まされていくのでしょう。そのため、「特にヨットマンには神経質で偏屈な人が多く」、陸の一般社会から誤解されてしまうこともあるそうです。
田久保さんにしても、九死に一生を得た大事故の後からは、“安全の鬼”として常に不測の事態に対する心の準備を怠りませんでしたから、彼らの人間性は素直に理解できたそうです。
「彼らは繊細な神経の持ち主ですが、話をしていくうちに実はとても大きな心の持ち主であることに気づかされます。細かい失敗を気にしていたら、航海という大きな目的は達成できませんから、ちょっとしたことではクヨクヨしない、物事を大きな視野で見る目を持っているのです。人間的に懐が深く、本当はやさしい心の持ち主なのです。繊細な神経と大きな心は、相反する人間性のように見えますが、実のところ、これらは表裏一体の関係なのです」
大きな心と繊細な神経を持つヨットマン。彼らの人間的な魅力は、会って少しでも話をすれば、すぐ感じ取れると田久保さん。腕の立つ剣士に向かって刀を構えたときに、「お主、できるな!」と察するような瞬間があるそうです。
「この場合の『お主、できるな!』という意味は、『お主、海を知っているな!』ということになります。ヨットに乗る者として、海を知っているさまざまな人と出会うことは、このうえない喜びです。安全に目的地に到着するため、あらゆる逆境と戦ってきたベテランヨットマンの話を聞きながら、彼らのチャレンジ精神に何度も感銘を受けました」
ベテランヨットマンのチャレンジ精神は、海に限らずあらゆる世界で参考になるはずだと、田久保さんは言います。
「ヨットで海に出てしまったら、乗員の力量とフネの耐航能力だけが頼りです。安全を第一条件にしながら、自分たちだけでさまざまな局面を乗り切っていかねばなりません。凪のときに立ち止まることはできますが、シケの海で何も対応しなかったら遭難してしまいます。全力を振り絞って走り抜くか、セールを小さくしてジッと耐えるか、あるいは引き返すか、自分たちで判断するしかないのです。
人間の人生とて同じことでしょう。家族に守られながら学校で勉強しているときは、いくらでも立ち止まって我が身を振り返ることができますが、社会に出て人生の壁に当たったときは、なんらかの決断を自分でしなければなりません。すべては自己責任なのです」

真冬の海に、オーバーナイト(昼夜をかけて長距離を走り続ける)の外洋レースに出ていく人たちがいます。ライバルたちと競いながら波に翻弄され、猛烈な寒さと戦うことになるので、『もう二度と出たくない』と最初は誰もが思うそうですが、なぜか次のレースが来ると、ほとんどの人が参加してきます。
その理由は、皆、よく分からないそうですが、ゴールしたときの達成感や、陸に戻ったときの安堵感など、その感激は例えようもないものだとも言われます。ひとつのレースに人生が凝縮されていて、このような感動が、生きる自信を育んでくれるからではないでしょうか。
「自分が経営する会社が傾いたり倒産したりして、泣く泣く愛艇を手放すヨットマンを何人も見てきましたが、その後、見事に事業を立ち直らせたり、新しい会社をつくったりして、ふたたびヨットを手にした例もたくさんあります。彼らのバイタリティは海で培われたものに違いありません。人生のゴールとは限られたものではなく、人それぞれであり、そこへ辿りつく道は、実にいろいろあるものだということを、彼らから教えられたものです」
制作・企画部で出版プロデューサーとして腕を振るった田久保さんは、数年後の1990年にメイン雑誌であるKAZIの編集チーフに任命され、1996年(3月号から)には取締役編集長に抜擢されました。70余年の歴史を数えるKAZI誌において、社員からの生え抜き編集長は初めてのことでした。広告部、企画・制作部と、いろいろな部署で積んだ豊富な経験をメイン雑誌であるKAZIで生かすチャンスがやってきました。

さまざまな外国人の質問をきっかけに、あらためて国内のプレジャーボート事情を整理した田久保さんは、愕然としました。分かってはいたものの、プレジャーボート先進国と呼ばれている国々に比べて日本の市場があまりにも小さいことを痛感したからです。
「このことを正直に話すと、彼らは『日本は四方を海に囲まれているのに、どうしてプレジャーボートが普及しないのだ?』、『経済大国でクルマもよく売れているのに、なぜプレジャーボートは売れないのか?』と言って不思議がりました。『戦後の復興を急ぐため、海岸線は産業優先になってしまった。そのため、マリーナなどに転用するにはいろいろな規制をクリアする必要がある』などと国内事情を説明しても、『規制があるなら、それを変えればいいじゃないか』とあっさり返されてしまい、こちらは困惑するばかりでした」
国内事情を説明しても、なかなか理解してくれない外国人。しかし、彼らの言うことはストレートで、ある意味、理にかなっている部分もあると感じた田久保さんでした。
「四方を海に囲まれていることなどは明白な事実です。しかも、これまでの日本には外貨を獲得すべく輸出産業を優先しなければならない事情がありましたが、今後はプレジャーボート産業などの内需も拡大していかねばならない時代です」
そのために、自分で何ができるだろうか。自問自答を繰り返していたある日、雑誌の仕事とは別にジャーナリストとして社会に働きかけていく道筋が生まれました。海洋系雑誌社の編集長やフリージャーナリストたちが中心になって、MJC(マリンジャーナリスト会議)という団体が立ち上がり、田久保さんも発起人として名を連ねることになったのです。
「出版社の垣根を越えてプレジャーボートの普及に手を携え、必要があれば国土交通省や自治体などにも積極的に提言していこう」。それが、MJC創立の理念でした。 (※続きます)