|

 |
|
アフリカでマナティの撮影
|
鳥羽水族館の館長さんから「大学を出たらウチに来いよ」と声を掛けられていた森さんは、パラオの生物学研究所へ行くことを大学の恩師から勧められて大いに悩みます。パラオの生物学研究所といえば、戦前にサンゴ研究の基礎を築いた世界的に有名な研究所(パラオ熱帯生物研究所)が置かれていたところであり、そのような場所で勉強することができるのは、またとないチャンスだったからです。
「悩んだ末、事情を説明したうえで『就職するのを1年だけ待っていただけないでしょうか』と館長さんに相談しました。すると、『就職は半年先でいいじゃないか。残りの半年は、水族館からの出向という形で面倒をみてあげよう』と、実にうれしい言葉を頂戴することができました。就職先を決めてからパラオの研究所に行けるだけでなく、半年間は給料をいただきながら研究ができるわけですから、私としては願ってもないことでした。今でも、鳥羽水族館ならびに中村幸昭館長には育てていただいたという思いでいっぱいです」
晴れてパラオの地を踏んだ森さんは、研究スタッフとしてのほか所内の自然保護局にも所属し、密漁の監視にも従事。船に乗ってパラオの周辺海域をくまなく監視して回り、その際に生まれて初めてジュゴンと出会い、パラオオウムガイにも大きな興味を抱きました。
「オウムガイは何億年も静かに生き続けている、生きた化石です。大学の恩師からは、『科学者たる者、常に好奇心を持ち続けろ』と言われたものでしたが、私がオウムガイに魅せられたのは、何億年も生き続けていることに好奇心を抱いたからです」
高校時代、森さんは英語が大の苦手でしたが、大学に入ってからは専門英語という教科があって、すべて英語で授業を受けなければなりませんでした。最初は戸惑ったそうですが、大好きな海や魚の分野の英語だったため、苦手意識よりも先に好奇心が湧いて、とうとう学会の発表も英語でこなせるようになったそうです。このエピソードは、好奇心を持つことの大切さを示していると思います。
 |
| イモムシの唐揚げを試食 |
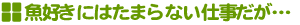
半年後、鳥羽水族館に戻った森さんはジュゴンの飼育を担当することになり、以後10年間、同水族館でジュゴンの飼育、研究に没頭しました。
「水槽で魚類などを飼育することだけが、水族館の仕事というわけではありません。飼育するために必要なノウハウを調査研究することも求められます。私の場合も、ジュゴンの生態を調べるため、毎年何回かはパラオやフィリピンなどへ足を運んでいました。自然界に生きるジュゴンが、どんなものを食べ、どんな環境で暮らしているのか、そのような知識を十分身につけないと、水族館で正しくジュゴンを飼育することができないからです。特に、私はジュゴンを扱うことが初めてだったため、こと細かく自ら現場に足を運んで知識を得たいと願いました」
調査研究は、長いときで半年間に及ぶこともあったそうです。海好き魚好きにはたまらない仕事ではありますが、人によっては向き不向きが出てきます。
「鳥羽水族館で調査研究のチームが組まれると、どういう訳か私はいつもメンバーの1人に選ばれていました。物おじしない性格で、どんな土地に行っても人の輪の中に入ることができるうえ、何でも食べられ、どこでも寝ることができたからだと思います。枕が変わったら寝られない人とか、現地でトカゲ料理などを出されて逃げ出してしまうような人は、この仕事には向いていないでしょうね」
水族館のスタッフといえば、多くの人が施設内で働く学芸員のようなイメージを抱きますが、いざ調査研究となれば、まるで探検家のような資質が求められます。そんな現場仕事を森さんは進んでこなし、ついに鳥羽水族館において世界で初めてジュゴンの長期飼育に成功。以後、さまざまな国で海洋生物の国際共同研究プロジェクトに参画するようになりました。
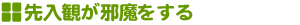
 |
| エルニドでジュゴンの馴致 |
森さんが飼育スタッフの1員としてジュゴンの長期飼育に成功した最大の理由は、水族館員の新人として1からジュゴンの生態を学んだことにありました。
「パラオの海でジュゴンと出会ってはいましたが、飼育の経験はまったくありませんでしたから、何もかもが未知の世界でした。そのため、ジュゴンのことなら何でも知りたい、もっと調べたいと、どんどん意欲が湧いていきました」
大学の恩師から、「常に好奇心を持ち続けろ」と言われた森さん。ジュゴンの長期飼育の成功は、その言葉をしっかり実践したことによるのではないでしょうか。
「すでに水族館勤務の経験があって、イルカなどの飼育経験や知識などをなまじ持っていたら、ジュゴンの飼育係には適さなかったかもしれません。経験も知識もなく、何の先入観もありませんでしたから、調査研究したことや現場で実際にジュゴンと触れ合った経験を、素直に受け止めることができました」
その後、さまざまな国際共同研究プロジェクトに招かれるようになった森さん。鳥羽水族館を退社後、ある時シンガポールの水族館からも赤ちゃんジュゴンの飼育を指導してほしいと頼まれました。
「その水族館に行ってみると、オーストラリアでイルカの飼育をしていたという担当者がいて、私が指導するたびに反論していました。私が何かしようとすると、『イルカではこうするはずだ』と来るわけです。しかし、相手はジュゴンです。『それはイルカの場合であって、ジュゴンではこうしたほうがいい』と説明するのですが、なかなか理解してくれませんでした。たとえばジュゴンには皮下脂肪がないため、皮膚注射をした場合は気をつけないと針が筋肉まで簡単に達してしまいますし、きわめて食道が細いので、イルカのつもりでカテーテル(栄養補給をするチューブ)を入れたら喉をつまらせてしまいます。これらは、すべて実践してみなければ分からないことであり、私の場合、彼のように先入観がなかったから身につけることができたのだと思います」
ジュゴンの専門家ではなく、大勢の人にジュゴンを知ってもらうための架け橋になりたい。そう願っていた森さん。ところが、水族館に入社して10年が過ぎると、職場の異動でジュゴンの飼育現場を離れることになりました。新しい部署は企画・広報や社会教育、イベントなどを担当する企画室。そこでは、まったく新しい仕事が待っていました。
|




