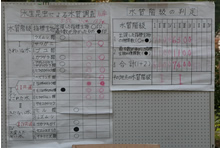|
|||
 |
|||
![]() 水に賢い子どもを育む年間型活動プログラム 高知県津野町葉山小学校の取り組
水に賢い子どもを育む年間型活動プログラム 高知県津野町葉山小学校の取り組

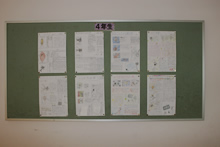 新庄川の調査レポートとは学校の掲示板に張り出してあります
新庄川の調査レポートとは学校の掲示板に張り出してあります レポートはわかりやすくまとめています
レポートはわかりやすくまとめています 今回の調査前に、インターネットなどで四万十川を調べました
今回の調査前に、インターネットなどで四万十川を調べました 4年生21名は、11時に町のバスで、今回の調査ポイントである旧東津野村の諏訪神社近くの一本橋に向かいました。諏訪神社の境内で今回の授業のゲストティチャーである元小学校教員で、前横倉山自然の森博物館副館長の高橋厚彦さんから、今回の授業のブリーフィングを受けました。高橋さんは1学期に行った新庄川の生物調査のときもゲストティチャーとしてレクチャーいただいています。このブリーフィングでは、新庄川の調査の復習と今回の調査方法について説明をいただきました。
そして昼食をはさみ、いよいよ四万十川の調査となります。神社下の畑を降り、川へ向かいます。踏みしめられた道を曲がると、そこには見たことのない橋がみんなを出迎えてくれました。
この橋こそが「一本橋」。四万十川といえば、川が増水したときに、川に沈んでしまう「沈下橋」が有名ですが、この一本橋も沈下橋と同じ考え方に基づき設置されているもの。ただし増水時には、この橋は水に流されてしまうよう設計されています。増水時に水に耐える橋を作るより、水には流されてしまうが、簡単に元に戻せる橋の方が、結果的には労力が少なく、維持管理が簡単であるという昔からの知恵。自然に逆らわず、共生する日本人ならではの考え方です。ちなみにこの橋は今でも生活道路として利用されています。子どもたちは、こんな話を聞き、実際に利用することにより学習につなげていくのも水プロの特徴です。
 このは橋はいったい!?
このは橋はいったい!? 町のスクールバスを利用して、四万十川まで移動しました
町のスクールバスを利用して、四万十川まで移動しました ゲストティチャーの高橋厚彦さん
ゲストティチャーの高橋厚彦さん この日はお弁当給食の日 外で食べる給食は格別!
この日はお弁当給食の日 外で食べる給食は格別! 水生生物の標本を参考に、四万十川の水生生物調査を行います
水生生物の標本を参考に、四万十川の水生生物調査を行います 四万十川に生息する生物などを集めたプリントを配布 東津野B&G海洋センターお手製です
四万十川に生息する生物などを集めたプリントを配布 東津野B&G海洋センターお手製です 初めての一本橋 落ちないように渡ります
初めての一本橋 落ちないように渡ります 調査ポイントに到着し、いよいよ川に入りますが、その前に安全学習を行います。安全学習を担当するのは、B&G財団職員の持田雅成。持田は、アトランタオリンピックのカヌー競技日本代表で国内外の急流をカヌー競技で経験している川のエキスパート。その経験を活かし、急激に変化する川の特徴や、どのようなところに危険が潜んでいるのかなど、実際の川を前にレクチャーしました。
この水プロ授業の特徴のひとつに子どもたちへの安全学習と、B&G指導者による安全管理があります。水の事故はひざ下15cmの水深でも起こることがあります。このような野外授業を行う場合、スタッフによる事前調査で川の状況を把握することはもちろんのこと、川底や水の流れを確認するとともに、前日からの天候や当日の天気図も考慮し、実施の可否を決めています。

 アトランタオリンピックカヌー競技日本代表でB&G財団職員の持田雅成による安全学習も実施
アトランタオリンピックカヌー競技日本代表でB&G財団職員の持田雅成による安全学習も実施  当日の水温は、5.5度 かなり冷たいです
当日の水温は、5.5度 かなり冷たいです 指標となる水生生物は、石の裏など隠れた場所にいます
指標となる水生生物は、石の裏など隠れた場所にいます
 水の冷たさも忘れて調査に没頭してしまいます
水の冷たさも忘れて調査に没頭してしまいます 少し珍しい生物を見つけると全員に報告「みつけたよ〜!」
少し珍しい生物を見つけると全員に報告「みつけたよ〜!」 水生昆虫をはじめ、小さな魚など様々な生物を見つけました
水生昆虫をはじめ、小さな魚など様々な生物を見つけました
■ 東津野B&G海洋センター指導者会もバックアップ!
B&G財団では、地域で行われる様々な事業を安全且つ積極的に展開できるよう、各海洋センターの指導者会の組織化について支援しています。今回の授業にも指導者会から、豊田庄二さんが駆けつけてくれました。豊田さんは、B&G指導者資格の「アクア・インストラクター」を取得し、東津野海洋センターの黎明期を支えた指導者の一人で、小さい頃に、魚とりなどでこの四万十川で遊び、今でもよく川に来る「川の達人」。そんな豊田さんが、子どもたちの学習を深められるよう、川魚を獲る「仕掛けかご」や、その仕掛けにかかった魚を持ってきてくれました。

 仕掛けにかかっていた「アカザ」 ひれに毒があるので要注意です
仕掛けにかかっていた「アカザ」 ひれに毒があるので要注意です 子どもたちは仕掛けに興味津々
子どもたちは仕掛けに興味津々 いろいろな魚を見ることが出来ました
いろいろな魚を見ることが出来ました
■ 調査の結果は....
四万十川の調査を終え、学習会場を神社の境内に移し、見つかった水生生物の報告と、生物指標による新庄川との比較を行いました。
気になる結果は.... 今回の調査では、新庄川と同様「きれいな水」に属することがわかりました。しかし、見つかった生物の違いから新庄川よりも少し汚れているという驚きの結果となりました。
なぜ、新庄川より上流の四万十川の方が少し汚れているのか? 葉山小学校4年生の学習はまだまだ続きます。
なお、今回の授業はテレビ高知の「がんばれ高知!!eco応援団」の取材を受けました。授業の様子は、11月8日の午前10時55分から放送されます。ぜひご覧ください。

 見つけた生物を発表し、表に書き入れます
見つけた生物を発表し、表に書き入れます カワゲラやヘビトンボなどきれいな水に住む昆虫を見つけました
カワゲラやヘビトンボなどきれいな水に住む昆虫を見つけました 残念ながら汚れた水に住むヒラタドロムシも見られました
残念ながら汚れた水に住むヒラタドロムシも見られました