 この日は、B&G財団職員が外部講師として参加。海岸に足を運んで磯の生き物を観察するとともに、なぜ干満があるのかなど、海で見られる自然現象について考えたり、深場に足を取られてときの対処の仕方などを学びました。 この日は、B&G財団職員が外部講師として参加。海岸に足を運んで磯の生き物を観察するとともに、なぜ干満があるのかなど、海で見られる自然現象について考えたり、深場に足を取られてときの対処の仕方などを学びました。 |
| |

|
 |
 |
| B&G職員とともに、紙コップやインスタント麺の容器を使い、インスタントの水中眼鏡を作りました。 |
磯の潮溜まりでの採集活動では、カニ、ツブ貝、ヤドカリ、稚魚、ヒトデなどが見られ、その数と豊富さに驚き、夢中になっていました。
|
カニを発見。注意深く観察すると、いろいろな生き物が生息しています。
|
 |
 |
 |
| 磯での活動を終えた後は、ふだんはなかなかみることができない海の生き物について、学びました。 |
| 割り箸で囲っていたはずなのに、まんまとヒトデは脱出に成功。 |
瀬棚町B&G海洋センター平山さんによる安全指導。深場に足を取られたときにどうなるかを学びました。 |
| |
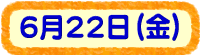 17日の磯での体験活動をもとに、「ヤマメ」と「サクラマス」を題材に川と海との違いについて考えました。 17日の磯での体験活動をもとに、「ヤマメ」と「サクラマス」を題材に川と海との違いについて考えました。 |

|
まず初めに,川で採れた生き物と海で採れた生き物の違いを取り上げました。川にいたヤマメの中で海へ降りるものがいて,それがサクラマスになるという事実を教師から提示。
20cmほどのヤマメと70cmほどのサクラマスの魚体の大きさの違いを実物大の写真で実感した子どもたち。
「同じ魚なのに,棲む場所が変わるとどうしてこんなに大きさが違うのだろう?」という問に
「えさが違うからではないだろうか?」
「海は大きくて広いから,生き物も大きくなる。」
「海の水には塩分があるから何か関係しているかも。」などの子どもたちの意見が出てきました。
17日(金)に磯で見た生き物の豊富さから,「海にはえさがたくさんある。」「大きな生き物もたくさんいるから。」などの考えが強い傾向となりました。
|
そこで,「この前たくさん生き物がいたのは磯の潮溜り。海の中にもたくさんいるのかどうかわかるかな?」の問いかけに,調べる方法を考え始めました。
「図鑑で調べる」「インターネットで調べる」「図書館に行く」など,初めのうちはバーチャルな方法ばかりが出てきました。しかし,ある子が黒板の図を指さして「こっち側(陸上)の方法ばっかりだ。」といった発言がきっかけとなり,実際に海へ行って調べる方法を考え始めま
した。
「船に乗って海へ出てみる。」
「釣りをしてどんな魚がいるか調べる。」
「わなをしかけてつかまえる。」
「ダイビングでもぐって海の中を見る。」
こうして,子どもたちはサクラマスのえさになる生き物が棲む海の中に一歩を踏み出していくのです。
|
 |
 |
| |
| 瀬棚小学校白川教頭先生は、「5月に行った馬場川での観察で、子どもたちは、ヤマメの仲間が海に出て大きなサクラマスになって戻ってくることに、大変興味を示し、川と海の関係について関心を寄せるようになりました。こうして、一つのことをきっかけに、いろいろな面で知識欲が生まれてくることに、この授業のすばらしさを感じます」と語ってくださいました。 |



