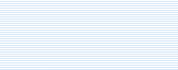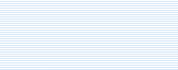|

�@���w�R�N���̂Ƃ��A���b�g�`���ƂƂ��ċr���𗁂тĂ����x�]���ꂳ��̒����ɏo��������Ƃ��A�l�������߂��ƌ�鉪������B�v���͑����m�ւƗY�A�����A�n�}�߂Ă͓��{����A�����J���C�݂܂ł̍q�H�ɕ`�������������ł��B
�@ �u���Z���ɂȂ�ƁA�W���������Y�Ȃǂ̕Y���L��ǂ���悤�ɂȂ�A�����m�͊C���ɏ���Ď��R�ɓn��邱�Ƃ�m��܂����B�������Ȃ��ŁA�����Y�����Ă��邾���ł�300�����炢����Γ��{����A�����J���C�݂ɒH�蒅�����Ƃ��ł���̂ł��B����Ȃ�A�����œn���Ă݂悤�I
�����炭200��������s����̂ł͂Ȃ����H ����ȕ��ɍD��S���ǂ�ǂ�c��܂��Ă����܂����v �u���Z���ɂȂ�ƁA�W���������Y�Ȃǂ̕Y���L��ǂ���悤�ɂȂ�A�����m�͊C���ɏ���Ď��R�ɓn��邱�Ƃ�m��܂����B�������Ȃ��ŁA�����Y�����Ă��邾���ł�300�����炢����Γ��{����A�����J���C�݂ɒH�蒅�����Ƃ��ł���̂ł��B����Ȃ�A�����œn���Ă݂悤�I
�����炭200��������s����̂ł͂Ȃ����H ����ȕ��ɍD��S���ǂ�ǂ�c��܂��Ă����܂����v
�@�v����������ő傫�ȕǂɂ����ʂ��܂����B����́A���������Ŗ`���q�C�ɏo�����w�ւ̐i�w�͒f�O���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł����B
�@�u�傢�ɔY�݂܂������A�X�� �j����̏����w�V���Ɉ�ԋ߂����x�̂Ȃ��Ɂw���̂܂܂ɂ����A���̎����Ɍ������ēw�͂��邱�Ƃ��A�����邱�Ƃł���x�Ƃ������肪�����āA�����ǂƂ��ɐS�̒��̃�����������C�ɐ���܂����B����܂ŁA�����m�𑆂��œn�����l�͂��Ȃ������ł�����A����ȒN���������Ƃ̂Ȃ����ɒ��킵�Ă݂����B�B���ł��ăq�[���[�ɂȂ�Ƃ������A��肽���Ǝv�������Ƃ����Ȃ��Ō���������Ȃ��Ƃ����C�����ł����v
�@���������邽�߂ɂ́A����Ȃ�̎������K�v�ł��B��������͉F���H�ƍ������w�Z�𑲋Ƃ���ƁA�����ɂȂ�ƌ���ꂽ��������D�ɏ�荞�݂܂����B
�@�u���Ƃ̍ہA�S�C�̐搶����e�q�ŌĂяo����āw���O�A�{���ɋ��D�ɏ��C�Ȃ̂��I�x�Ɩ₢�l�߂��Ă��܂��܂����B�w�Z�ɂ́A�i�w�ɔ����ĂP�N�Q�l����ƌ����Ă����̂ł��B�搶�͂��Ȃ�{���Ă��܂������A�Ō�ɕꂳ�����Ȃ���w�搶�A����̌������͖ق��Č��Ă����Ă��������B�i�����m���f�́j����Ă݂ă_���Ȃ���߂����͂��ł�����x�ƌ����Ă���܂����v
�@�����m���f�͐e�s�F����̋ɂ݂������ƁA��������͓�����U��Ԃ�܂��B�x�]����̖{��ǂ�Ŏ�������������ǂ������ƌ��ɏo���n�߂����w�����ォ��A�����m��n���ċA������܂ŁA���e�Ƃ͌��𗘂������Ƃ��Ȃ������Ƃ����܂��B�����ł��`���̘b������ƌ��܂ɂȂ��Ă��܂�����ł����B
�@�u�����Ƃ��A�ꂳ��͕ʂł����ˁB��x���~�߂�Ƃ͌����܂���ł������A�o�q�̍ۂ��Ί�ő����Ă���܂����B�������A���b�g�Ȃ�ď�������Ƃ��Ȃ������̂ł�����A���d�Ƃ����Ζ��d�Șb�������Ǝv���܂��v
�@��e�̗����ɏ������ċ��D�ɏ��悤�Ȃ�����������B���̌�A�����̍����d�������߂ĉݕ��D��^���J�[�Ȃǂ����p���A�呲���C�����U���~�̎���ɁA�Q�N���قǂ�350���~���̒�������ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B
 �@
�@
�@�\���Ȏ�������ɂ���ƁA���I�т��n�܂�܂����B�������ڎw�����̂͑����m���P�l�ő����œn�邱�Ƃł������A�ŏ��ɁA����l����u���b�g�łȂ���ΊC�O�n�q�͔F�߂��Ȃ����낤�v�Ƃ����w�E���Ă��܂��܂����B
�@���Ȃ݂ɁA���b�g�ł̊C�O�n�q���x�]���ꂳ�����m��n������ŁA�悤�₭�F�߂��܂����B�����A�x�]����̓��b�g�ł̏o���͔F�߂��Ȃ����Ƃ�m���Ă������߁A��ނȂ����o���̌`�ő����m��n��܂����B���̂��߁A�T���t�����V�X�R�ɒ������Ƃ��ɂ͓��{�̃}�X�R�~����ƍߎ҈�������Ă��܂��A�@���Ȃ��A�����J���{�ɋ������҂����߂܂������A���̂悤�ȏ��@�m�����T���t�����V�X�R�s�����@�]�𗘂����Ėx�]����𖼗_�s���Ƃ��Č}������A�������҂�j�~���Ă��ꂽ�̂ł��B������ē��{�̊e�}�X�R�~���x�]������q�[���[�Ƃ��Ĉ����悤�ɂȂ�A���̌�A���b�g�ł̊C�O�n�q���������悤�ɂȂ�܂����B����䂦�A�x�]����́u�P�Ƒ����m���f�v�Ɓu���b�g�ɂ��C�O�n�q�̎��R���v�Ƃ����Q�̖`����B�������Ǝw�E����l�����Ȃ�����܂���B
�@���āA��������̓x�e�����̃��b�g�}����b�g�v�҂Ȃǂ��炳�܂��܂Ȉӌ����ĉ��A���z�I�Ȉ����̎p��ǂ����߂܂����B
�@�u�v�́A���b�g�ł���Ώo���ɖ��͂Ȃ��킯�ł�����A���b�g�̐}�ʂ���ɁA�����ڂ������b�g�ɂ��āA�}�X�g�͂����Ɏ��O����悤�ɍH�v���܂����v
���e����H�����������ɁA��������͗c��������H����g�����ƂɊ���Ă��āA�x�]����̖`���Ɋ������ꂽ���w������ɂ͑S��4m�̃{�[�g���A���ꎞ��ɂ͑S��5m�̃��b�g���������Ă��܂����B�����m�ɏo�鈤���́A�S��21�t�B�[�g�i��6.3m�j�̃��b�g���x�[�X�ƂȂ�܂����B��������́A�P�l�Ō����Ɏ��|����A���b�g�ɏڂ����l�̃A�h�o�C�X��������āA�����͓̂`���I�ȘE�i��j�Ƃ��܂����B
�@�u�ŏ��̓I�[�����l���Ă��܂������A�E�͉������Ƃ����������Ƃ������i�͂������܂����������������ł��v
�@��������͓Ɗw�ŘE�̑��������}�X�^�[�B�������[�A�o�q�̓���҂��܂����B

�@1976�N�A23���}�����N�ɁA�悤�₭���������Ƃ�������Ă��܂����B�����m�𑆂��œn��Ƃ͒N�ɂ������Ă��܂���ł������A���胈�b�g�ł̃`�������W�͓��{���Ƃ������ƂŘb��ɂȂ�A�����̐l��������ɗ��Ă���܂����B
�@�u����ȂȂ��ł��A�������͂Ђƌ��������J���Ă��ꂸ�A�����ق��Ĉ�������Ă��ꂽ�����ł����v
�����A�l�C�̂������̎�ʼn����������t�@���������Ƃ����� ���D�̃j�b�N�l�[��������ɂ����q�V���V�AIII���r���i����R�ǖڂȂ̂�III���j�́A�����ɃZ�[�����O�œ쉺�B���䓇���ɓ��������i�K�ŃZ�[���ƃ}�X�g�����O���A���悢��E�����𗊂�ɐj�H���A�����J�嗤�����܂����B
 |
| �V���V�A�[�� |
�@�u�o�q�������A���e����n���ꂽ�d���ٓ̕���m��ŊJ���Ă݂�ƁA��i�ڂɁu�����I�@��v�Ƃ����Z���莆���������܂�Ă���A�����ē�i�ڂ��J���Ă݂�ƁA�Ȃ�Ɓu�����ċA��I�@���v�Ƃ����莆������܂����B����܂Ō��𗘂������Ƃ��Ȃ�����������ł������A���͎��̂��Ƃ������ƌ�����Ă��Ă��ꂽ�̂ł��B���̂Q�̎莆�́A�r�j�[���܂ɓ���đD���ɓ\���Ă����̑���ɂ��܂������A�܂����݂����Ď~�܂�܂���ł����ˁB������U�N�O�A���R�ɂ��D���̗l�q�ƂƂ��ɂ��̎莆���ʂ��Ă���ʐ^����ɂ��邱�Ƃ������āA�悭����Ǝ��͂Q�̎莆�̕M�Ղ͂Ƃ��ɕ�����̂��̂ł����B���̎�����m��̂�20�N�߂����������Ă��܂��܂������A���炽�߂ĕ�����̈���m�邱�Ƃ��ł��܂����v
�@�E�ő����n�߂�3���ځA�u�����ċA��v�ƂЂƌ������`���Ă��ꂽ���e�̋C�����ɕȂ���Ȃ�Ȃ��o���������X�ɂ���Ă��܂����B
�@�u�J���~��o�����̂ŁA�g�͍��������̂ł����f�b�L�ɏo�đ̂�A���ւ��邽�߂ɑD���ɓ������u�ԁA�S�[�Ƃ������ƂƂ��Ɉ�C�ɓ]�����Ă��܂��܂����B����ĂđD�����甲���o���ċ~���C�J�_�ɏ��ڂ�ASOS�̔��M���������Ă���ƁA���X�����b�g�ł���������N�������Ă���܂����B�������A�~���C�J�_�ƒ�������ł������[�v�͂��łɐ�Ă��āA�ǂ�ǂ�����牓�������Ă�������ł��B�~���C�J�_��������15m�ȏ㗣���ƁA����������ł��郍�[�v�͎����I�ɐ��悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B�w���܂����I�x�Ǝv���܂������A�Ȃ�Ƃ���܂ŗ����ނ�����邽�߂ɑD�����痬���Ă����ނ莅���~���C�J�_�ɗ���ł��邶��Ȃ��ł����B���鋰��ނ莅��������Ăǂ��ɂ����ɖ߂邱�Ƃ��ł��܂����B�������͐_�l�̂������������ƌ����ق��͂���܂���v
�@�ق��Ƃ���̂����̊ԁA���x�͑D���ɂ��܂����C�������ݏo���˂Ȃ�܂���B��ӂ������ăo�P�c�ŋ��ݏo���܂������A�ǂ����炩���R�ꂪ�N���Ă��邱�ƂɋC�����܂��B
�u����ł͍q�C�͖������Ɣ��f�B���Ă����}�X�g�ƃZ�[�������o���A�Z�[�����O�ŗ��n��ڎw�����ƂɂȂ�܂����B����ƁA�P�ǂ̋��D�Ƒ����������߁A�ꂳ�ĂɁw�����Ԃ��x�|�̓d���ł��Ă����悤���肢���܂����v
�@�ً}���ԂŎd�����Ȃ������Ƃ͂����A�����Ԃ��Ȃ������������́A����ŗǂ������̂��ǂ����傢�ɔY�݂܂��B�D���C���ɓ����Ŗc���������߁A���R�ꂪ�~�܂�n�߂Ă������Ƃ��C�����h�����܂����B
�u�Q���قǂ����āA�܂��ʂ̋��D�Ƒ����B���x�́A�w��͂�s���x�Ƃ̓d��𗊂�ł��܂��܂����B�l�Ԃ̈ӎu�́A�v���Ă���قNj������̂ł͂���܂���B���̏ꍇ���A���̂Ƃ��͋��������Ǝア�������i���������Ă��܂����ˁB�ł��A���Ԃ����̊������������Ă���܂����B���Ԃ́A�l�̐S�̏�������ė�ÂȎ��������߂��菕�������Ă����̂ł��B���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA�A�낤�Ƃ�����C�ȕ������i�X�Ɣ��炬�A�A�鋗�������O�i�߂Γ��t�ύX�����炢�܂ł͍s���邶��Ȃ����Ƃ����A�O�����ȋC�����������Ȃ��Ă����܂����v
��������́A����ŗǂ������̂�������܂��A�u�A��v�A�u�s���v�Ƃ����d��𗧂đ����Ɏ���e�ɂ��Ă݂�A���܂������̂ł͂���܂���B
�@�u��ŕ������b�ł����A�w�����Ԃ��x�Ƃ����d�����ɂ����Ƃ��́A����ł����ƃz�b�Ƃ��������ł��B�ł��A�����āw��͂�s���x�Ƃ̒m�点�����Ƃ��́A����͑�ςȂ��ƂɂȂ�Ǝv���������ŁA�_�Ђɍs���Ă��S�x�Q������������ł��v
�@�ʏ�A���b�g�Ȃ�x���Ă�80�����炢����A�����J�ɓ��B�ł��܂��B�������A���������l�����́A�܂��������œn���Ă���Ƃ͎v���Ă��܂���ł�������A80�����߂��Ă��A�����Ȃ����ߐS�z���͂��߁A100�����߂���������ő唼�̐l�����߂̋��n�ɒB���Ă��܂��܂����B
�@�u�A�����J�ɒ������Ƃ������ۓd�b���Ƃɓ��ꂽ�̂́A147���ڂ̂��Ƃł����B�d�b�ɏo���͕̂ꂳ��ł������A��b�킩��Ȃ��Ȃ������������Ă��܂���ł����B������͗���ł������A�Z�����̖�����m�点�ɑ���ƁA�ق��ĉ��������ċ����Ă��������ł��v
�@���̍q�C�͐e�s�F�̋ɂ݂������Ɖ�������͉��x�������܂����A�����Ƃ��Đe���ǂ�ȑ��݂Ȃ̂����v���A�ƂĂ��ǂ��@��ł��������Ƃ��m�����ƌ����܂��B���ہA���̍q�C�Œm�肦���e�̈��Ƃ������̂��A���̌�A��������̎d���̂Ȃ��ő傫�ȈӖ��������ƂɂȂ��Ă����܂��B
|