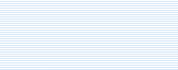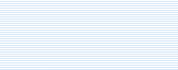|

これまで私は大学教員の立場から体育学や医学を教えてきましたが、こうした経験を経て健康予防の大切さを考えるようになりました。医学的に言えば予防医学ということになりますが、いずれにしても「予防」ということは個々の問題というよりも社会的なテーマになっていきますから、体育学や医学のみならず、もっと別の視野で物事を見る目も必要になります。体育ということでは、体育学を学ぶ生徒のみしか教えられませんし、また、私は医科学センターで患者さんに応対していますが、その数は年間に8,000人程度と社会的に見たら限りがあるわけです。健康予防というテーマに取り組むのであるなら、もっと一般的で広い世界を対象にしていかねばならないのです。
 私は、20歳代で体育学に取り組み、30歳代では救急救命の観点からスポーツ医学に取り組んできました。そして、いま40歳を超えたところで、そろそろ次のテーマに取り組むべきではないかと考え、これまでの経験を基に今年からは社会学部で教えることにしました。いま述べた健康予防というテーマを考えていくうえで、私自身にとっても社会学の視点が必要であると考えた結果です。 私は、20歳代で体育学に取り組み、30歳代では救急救命の観点からスポーツ医学に取り組んできました。そして、いま40歳を超えたところで、そろそろ次のテーマに取り組むべきではないかと考え、これまでの経験を基に今年からは社会学部で教えることにしました。いま述べた健康予防というテーマを考えていくうえで、私自身にとっても社会学の視点が必要であると考えた結果です。
教鞭を執るのは、流通経済大学と中央大学です。法学部の場合は、私は法のリーダーになる人たちへ、この連載記事でも語らせていただいている危機管理におけるヒューマニズムを伝えたいと考えました。当初、法学部教授との会話にて、「授業のテーマは危機管理にしましょうか」と進言したところ、「いや、そうではなくてライフセービング特論そのままを使いましょう」と、逆にリクエストされました。つまりは、私が説くところのライフセービング・フィロソフィー(参照:前号、前々号)を、教授はしっかり理解してくれていたのです。
ライフセービングを授業で学ぶと聞いて、法学部の学生たちは戸惑うことでしょうが、何も水泳キャップをかぶって海に入ったり、浜に出てトレーニングをしたりするわけでもありません。これまで述べたようなライフセービング・フィロソフィーの発想で、いろいろな社会的テーマについて考えていくということになるわけです。
常に社会は動いていますから、テーマは尽きることがありません。この連載でも取り上げたように、津波や地震、そして人間の命は復活すると思っている現代の子どもたちの姿など、1つの社会的な出来事について、「私ならこう捉えるが、君ならならどうする」といった投げかけによって、実にさまざまな答えが浮かび上がってくることと思います。
ですから、授業そのものも毎年のようにどんどん変化していくことでしょう。そうしたなかで、私はライフセービング・フィロソフィーの考えから生まれるヒューマニズムを彼らにしっかり伝えていきたいと考えています。
 
大学で社会学部を教えることになったほかに、もう1つ、私が取り組み始めた仕事があります。それは、世界で初めて日本にできた救急救命士の大学院で講義を行うようになったことです。ここでの講師は全員が医師で、私だけが体育学の専門です。
大学院におけるそのご縁を考えれば、救急救命の場合、医師は患者を待つしかないという現状があるからです。救急救命は、現場での処置如何でかなりの差が出てしまいます。救急車が来るまでには早くても6分かかると言われますが、この間にどれだけの処置ができるか、そこに大きな意味があるわけです。
医学的には、脳が生きる限界は呼吸が停止してから4分だと言われていますが、救急救命を受ける人が、この4分の間にどんな状況に置かれていたのかということを、病院で待つ医師は知るすべがありません。しかし、まさに私は救急救命の現場を経験してきているわけです。つまり、救急救命の世界も医師のもとへ運ばれてきた人を助けるという意識から、現場で事前に手を打つという意識に大きくシフトしてきているからなのです。
救急救命センターに運ばれてくる人の大半は、脳細胞が酸素虚欠の状態になっています。この状態では、いくら心臓や肺機能が快復して息を吹き返しても、意識はなかなか戻りません。つまり、このような仕組みでは、社会復帰ができない、復帰できたとしても大きな障害を負ったままになってしまう命を、社会がたくさん抱えてしまうことになります。ですから、数多くの救急救命センターが、現場で事前に手を打つことができて社会復帰が望めるようなケースを少しでも増やしたいと願うようになってきました。
では、救難の現場で事前に手を打つことができるのは、いったい誰でしょうか? それは病院にいる医師でも、救急車で駆けつけてくれる救急救命士でもありません。海水浴場であればライフセーバーに頼ることも期待できるでしょうが、救難現場が地震に見舞われた自宅や町中だったら、それも叶いません。できるとしたら、倒れた人のすぐそばにいる人以外にあり得ないのです。そう、それは皆さん1人1人なわけなのです。ですから救急医学の世界では、現場に居合わせた誰もが事前に手を打つことができるような教育に、力を入れ始めているのです。
ライフセービングには、バイ・スタンダー(By Stander)という考え方があります。すなわち、倒れた人の命を助けることができるのは、すぐそばにいる人に他ならないということです。愛する人や家族にとってのバイ・スタンダーとは、いったい誰でしょうか。それはあなた自身なのです。
新潟中越地震では、3世代、4世代が共に暮らす家が災害に見舞われてしまいました。そのときの、バイ・スタンダーは孫の世代にあたる若い人たちでした。前々回で述べたように、いざというときにお祖父さんやお祖母さんを抱えて逃げることができるよう、日頃から体を鍛えておくのも「事前に手を打つ」ための方策の1つです。
それは、言われてみれば簡単に理解できますが、言われてみなければ、そのために体を鍛えるという気持ちは、なかなか出てこないと思います。知ると知らないとでは、いざというときに大きな差が出てしまいます。だから、教え伝えるという教育が大切な意味を持ってくるのです。
厳しいことを言うようですが、いざというときに愛する人を抱えて逃げるだけの力を持っているかどうかは、あなた自身が問われる問題なのです。
|