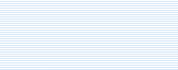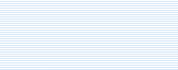|
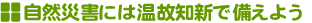
私は日本ライフセービング協会の理事長を務めていますが、私が掲げる究極の目標は協会を解散させることにあるんです。皆さん、一人一人が救急救命法を身につけていたら、ライフセーバーは必要ないからです。まあ、それは現実的に不可能だとしても、自分や家族を守る教育をより多くの人にしてあげることができたら、事故そのものは減ると思いますし、地震や津波といった自然災害を受けたときにも命を危険にさらす場面が少なくなると思います。
地震といえば新潟県中越地震が記憶に新しいですが、この地震は阪神淡路大震災のような都会での地震と異なり、3世代、なかには4世代が同居するといった大家族が多く暮らす地域で発生した点に特徴がありました。つまり、山崩れが迫るなかで孫の世代の若者がお祖父さんやお祖母さんを背負って逃げなければならなかったのです。ですから、このような地域では、常日頃から若者は老人を背負って逃げるだけの体力を備えておくべきだと感じました。
最近、災害に対する危機管理が叫ばれるようになりましたが、ひと口に危機管理と言っても、このように地域や家族に求められる個々の対策を付加しなければ成り立ちません。大きな地震は、50年とか100年に一度あるかないかといった実にインターバルの長い現象ですから、それに対する備えはなかなか難しい面もありますが、自然災害には過去の事例があるわけですから、それを教訓にして未来に備えるという温故知新の考えが大切です。50年、100年というインターバルを冷静に考えてみれば、人生のなかで1度ぐらいは大地震に遭遇する可能性があるわけで、もし出会ったら致命傷を負わない保障はどこにもないのです。
また、スマトラ沖で起きた未曾有の大津波では20万人以上の人が犠牲になりましたが、海洋学者に言わせれば「地球にしてみれば微妙に回転がブレた程度で、どうってこともない現象」なのだそうです。人間とは、なんと小さい存在なのでしょう。ですから、自然に対する畏敬の念を持たねばなりません。その上で、自分たちに何ができるのかを考えることが大切です。そのためには、限られた状況のなかで必要と思われるライフラインを自分たちで補うという、野外キャンプなどの体験的な教育が必要だと思います。B&G財団では数々の自然体験プログラムを行っていますが、実はこうした活動は危機管理の教育につながっているのです。
 
ライフセービングではビーチフラッグを取り合う競技がありますが、このビーチフラッグは傷ついた人を意味しています。つまり、いかに早く傷ついた人のもとへ行って、安心を与えることができるかを競っているわけであり、この意味を理解すれば競技に臨む選手の意識も大きく変わります。
このように、「命」というキーワードを使ってある行動や活動を見ていくと、それまでとは違った意味が表れてくる場合が多々あります。たとえば、キャンプは楽しいレジャーではありますが、流木などを拾って火を起こしたり、テントを張って夜露や寒さをしのいだりする行動は、実は命をつなぐライフラインの確保を意味しています。地震などの災害が起きたときは、道路が寸断されたり配車が間に合わなかったりして救急車もすぐには来てくれません。ひょっとしたら1日、2日と自分たちで耐えなければならないのです。こうした事態に遭遇した場合、自らの力で命をつなぐという行動は「できる、できない」ではなく「やるか、やらないか」という問題になってきます。そこまで追い込まれたら、人間はやるしかありません。
だからこそ、「やるしかない」という教育も必要なのだと思います。それは、火を起こさなければ食事ができないといったキャンプや、自分で風をつかんで走らなければ陸地に戻れないヨットといった、自然体験活動のなかに含まれています。ですから、実践を通じて結果的には自分や仲間の「命」の尊さに結びつく自然体験活動を、なるべく教育のなかに取り込んでいくべきだと考えています。
このほか、たくさんの人がダイエットとか生活習慣病の予防などといった理由から、日頃の生活のなかで健康づくりに励んでいますが、これも「命」というキーワードで考えてみれば生命の活性化という意味にたどり着きます。なぜ、多くの人が健康づくりに関心があるのかと言えば、実は、衣食住のことを連想しがちな「生活」という言葉の奥に「生命活動」という大きな意味が腰を据えているからなのです。太古の人々は、今日をどう生きるかが、すなわち生活だったわけです。ですから、同じ健康づくりでも今日の命を精一杯生き、次につなげるという自らの「生命活動」を意識することで、取り組む姿勢も大きく変わってくることと思います。
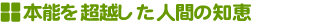
「命」という言葉をキーワードにしながら、キャンプやヨットといった楽しい活動を通じて、いざというときの危機管理能力を身につけるといった発想は、ライフセービングを通じて培われた哲学、ライフセービング・フィロソフィーによって理解することができます。ライフセービングという言葉から、多くの人が海水パンツとキャップを身につけたライフセーバーを連想しますが、私は、彼らライフセーバーたちに「海水パンツをはいていない、普段の生活を送っているときから常にライフセービング的な考え、すなわちライフセービング・フィロソフィーを持っていてほしい」と説いています。陸の上でも、いざというときに、どんな行動が取れるかが大切なのです。
 作家の司馬遼太郎さんは、「人のために尽くすということは、本能によるものではない」と語っていました。本能だけに従えば、動物と同じように弱肉強食の世界になってしまいますが、動物と違って人間は知恵をつけることができたわけです。知恵をつけたからこそ弱者を助けるという行為ができるようになり、「やさしさ」、「いたわり」、「慈しみ」といった気持ちを持つことができるようになったのです。 作家の司馬遼太郎さんは、「人のために尽くすということは、本能によるものではない」と語っていました。本能だけに従えば、動物と同じように弱肉強食の世界になってしまいますが、動物と違って人間は知恵をつけることができたわけです。知恵をつけたからこそ弱者を助けるという行為ができるようになり、「やさしさ」、「いたわり」、「慈しみ」といった気持ちを持つことができるようになったのです。
子供が転んだとき、親は「痛かったね」と言いながら手を差し伸べます。ここで1つ、知恵をつけた人間らしい行動が生まれたことになり、「どう?
大丈夫?」という、いたわりの言葉が生まれます。ライフセーバーが人を助けたときであるならば、「もう大丈夫だ!」という言葉によって救難者を安心させることができるわけです。
転んだ子供に手を差し伸べることができた親は、この経験を基に、今度は転んで血を流してしまった子供にも適切な対応を取ることができるでしょう。そうしたら、もし骨折した場合ならどうしたらいいか、万が一、呼吸が止まってしまった場合ならどうしたらいいか、といった知恵をつけていくことと思います。
ですから、救急救命の技術云々よりも何よりも、人をいたわるという考えそのものが人を助ける行為の基本になっているわけです。この考えを拡大していけば、民族間の助け合いにまでつながっていきますから、平和な社会をつくる根は「やさしさ」や「いたわり」といった、人間が人間であるために備え持った知恵にあると言えるのです。最近、人の命が簡単に脅かされる事件が相次いでいますが、その背景には、こうした教育がおろそかになってきたことも大いに関係しているのではないでしょうか。
|